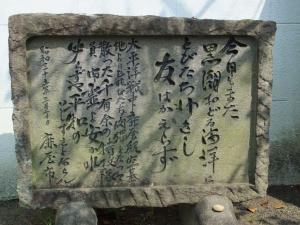《雑草(コラム) 》
失われた里山が与える影響は大きい~その復活の鍵は…
前回、「農」に加えて「食」の観点から地域の資源というものを考え直してみる…などと書いた。
この大隅半島は、食の供給基地としての役目を担っていて、鹿児島県の生産額ベースで自給率は令和5年度で261%、大隅半島はもっと高いと思うが、消費者、食べる側としての私たちは、その豊かさをあまり実感していない。
ただ前回書いたように、ここに来て令和のコメ騒動も含め農業に対するいろんな議論に触れてみると、大規模農家、スマート農業が中心だったりする。
そこもとても大事だが、この大隅半島に住んでいて、畜産が盛んで日本一、日本有数の産物があるように、大消費地に遠いということもあるものの、第一次産業に対する年間を通しての環境としてはとてもいい。
思うに、だからこそビルが立ち並ぶ都会でなく、北海道のように何㌶も田畑を耕してということでもなく、鹿児島県、そしてこの大隅半島における農のスタイル…というものがあるのではないか、そこをもっと突き詰めていくべき。
この地域により合ったスタイルの農業をみんなで考えよう!などと感じたりする。

写真=ファミリーが協力し合い自分たちの食べるお米づくり
今、高市政権になってから国会でも様々な課題についての論戦が続いている。そこではあまり表に出てこないが、日本の食料自給率、エネルギー問題も大事なことであり、加えて地方では今、少子高齢化、人口減少、中山間地にある小中学校の廃校等が続き、農地が荒れ果てている。
今、熊の出没が大きく取り上げられている。これまで山に入ったり自然と親しむことをしてきた身からすると、以前は、動物の住む自然と、人の住む市街地区との間に里山があって、その自然の豊かさをともに享受しながら、動物の暮らすエリアとの境界線、緩衝地域があり、そこも含め自然の中で動物と人間とが棲み分けられていた。
もちろんそれだけでなく、異常気象や、その影響で食べ物が足りなくなっているという現状もあるが、今、農家の高齢化で耕作放棄地が増え、住む人も減り、郵便局や学校もなくなり子どもたちが遊んでいた声や姿が消え、里山自体が消えてしまった。
つまり動物からすると、自然に中において生活する人の息吹を感じ、声や姿があったわけで、その緩衝地帯で言わば共存をしてきた。しかし今は、森に食べ物が少なくなって探しているうちに、失われた里山を飛び越えて直接異次元な世界へ、異次元な食べ物のある場所へ舞い込んでしまった。
鳥獣に対し無防備な市街地に住む人間からすると、「駆除」ということになってしまう。
中山間地の多い日本の農業の衰退はカバーできない…
話がちょっと逸れてしまったが、ただ、全く関係のないことでもない。
これまで田畑を耕してきた農家の方々が高齢となり耕作放棄地が増え、里山が消えてしまった。そうした環境の中で大型機械を使い、スマート農業を駆使して復活させる…、そんなことは現実的でなく今、その豊かな里山の暮らしに魅力を感じつつ、そこへ自分たちの意志で移住してくる人や、最小限の機械を使って、いくつかのファミリーが協力し合って手作業で、自分たちの食べるお米や野菜を作っていく、そうした人たちの集まり、そうしたことを企画する地域の元気な人たちが出現してきている。
何を伝えたいかというと、大型機械を使い、スマート農業を駆使する農業は、極端に言うと一経営体平均面積442㌶という米国、豪州や日本で言うと北海道、お米どころの東北、信越地方ではいいのかもしれないが、それだけでは、中山間地の多い日本の農業の衰退はカバーできないということは、農業関係者は分かっているはずだ。
識者の中には、天変地異の飢饉とかでなく、農政のまずさからどこかのタイミングで人災的に飢餓が起こるのではないかと言う人もいる。
それらを解決できるヒントは、自分たちの食べるお米や野菜を、自分や子どもたちのために「食べる」という観点から安心安全に作っていこうというムーブメントが、若い層を中心に少しずつだが動き出しているということなのか。
「食べる」という観点から若い層を中心としたムーブメント
耕作放棄地解消のみならず、そうした流れは、図らずとも貧困な日本の食料自給率を改めて考え、国の進めるこれからの「緑の食糧システム戦略」を自分たちのものとして捉え、試行錯誤しながら個々だけでなく地域全体で進めていくような地方こそが、その答えを出せるということなのだろうか…。
穿った見方かもしれないが、そうしたことを考えながら、さらにつらつら書いていきたい。(米永20251114)









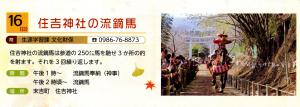























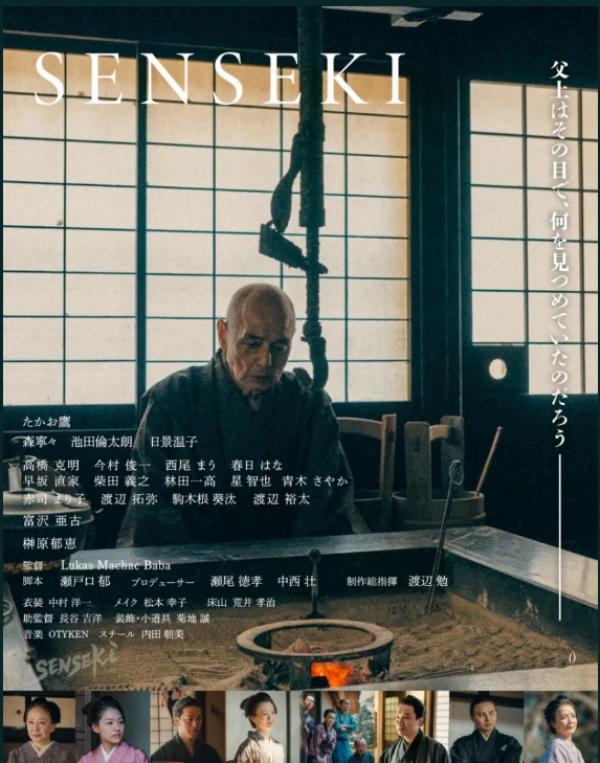

清掃活動20251025_251110_6_1024.jpg)



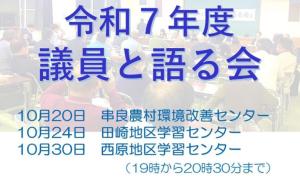























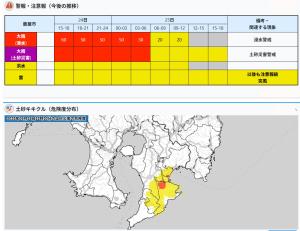





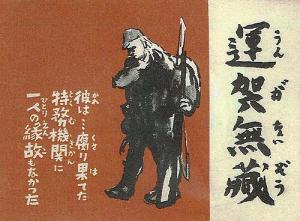



カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)