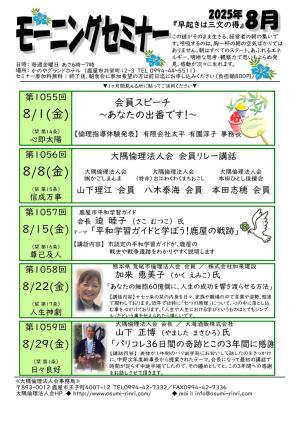2024年06月02日 07時37分







《歴史 》
難攻不落な山城、肝付城巡り~高山歴史研究会
高山歴史研究会はこのほど、肝付城(高山城)について、同会副会長で大隅史談会会員の福谷平氏の説明を受けながら、2時間以上かけ山城内を巡った。


福谷さんは、肝付城について、目の前の山全体が山城で、面積は50ヘクタールを越していて、周りに本城川、高山川、栗山川と3つの川が流れ囲まれている川が自然の堀の要塞。
また、見渡す限り山に囲まれている4山があり、山城としては理想的な場所にある。一回も落城していない。
築城は長元9年1036年、9月。最後は島津と和議して軍門に下るけど、阿多に移封される1580年までここにお城があった。


肝付氏はもともと大伴氏、途中で伴氏になる。
50代桓武天皇、第3子を大伴親王といい、のちの53第淳和天皇になる。天皇即位時に姓が同じじゃまずいということで
大伴の大を取られて伴とした…など説明。
城内を馬乗馬場跡、湯沸場跡、大来目神社、球磨屋敷、大手門、空堀、枡形跡、馬場乗場跡、土塁や曲輪、本丸跡、二の丸跡、一騎通し跡など約2時間かけ巡った。



高山歴史研究会の会員や一般参加もあり、「初めて城内を歩いてみました」「何回か来たことがありますが、こうして説明を聞きながらだと、とても勉強になりました」など感想を述べていた。









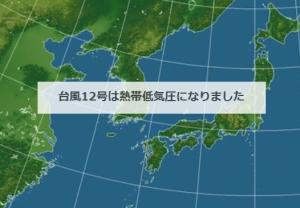

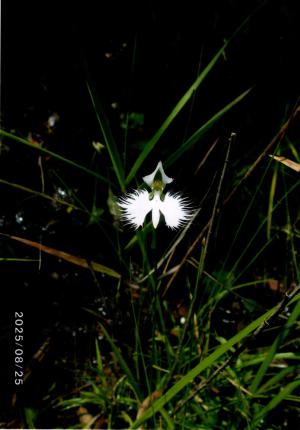
_(説明資料)滞空型UAV(シーガーディアン)の鹿屋航空基地への配備について_00002.jpg)



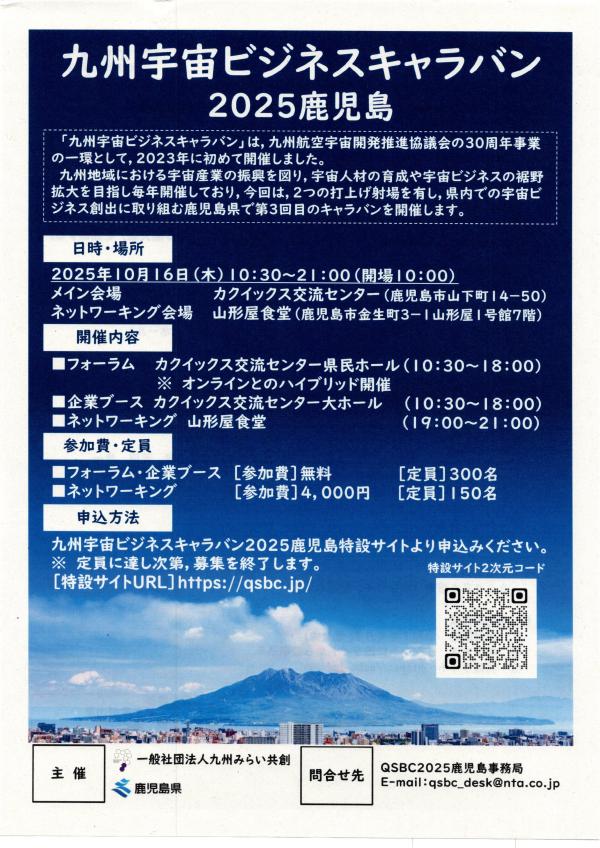



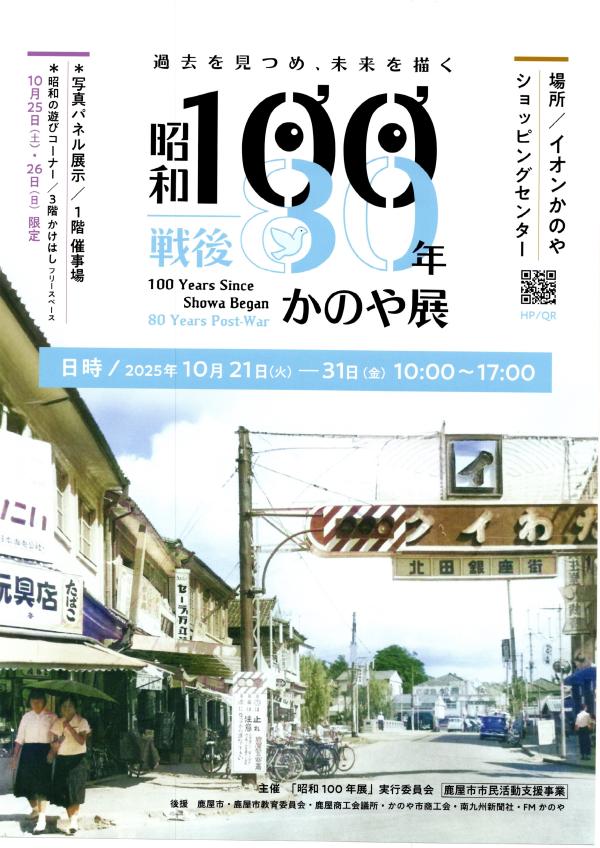

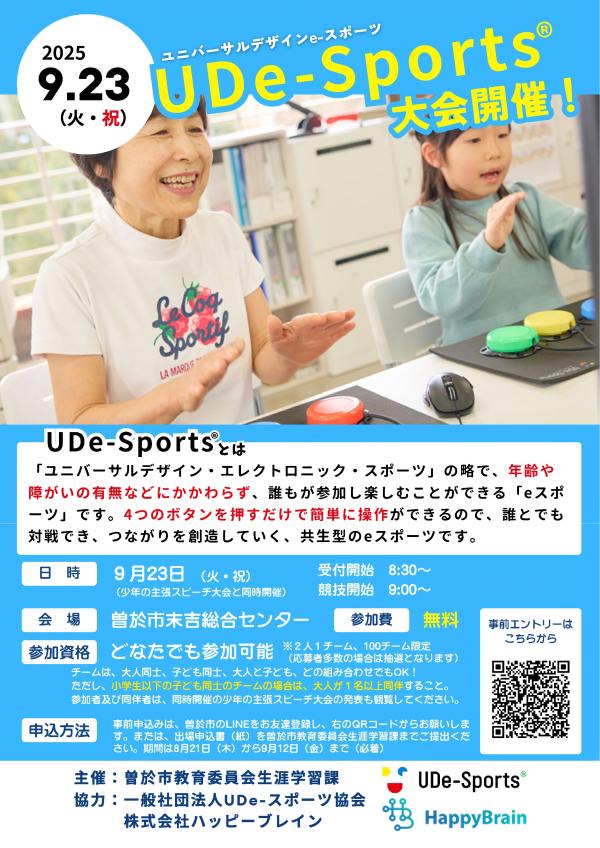
_(説明資料)滞空型UAV(シーガーディアン)の鹿屋航空基地への配備について_00002.jpg)

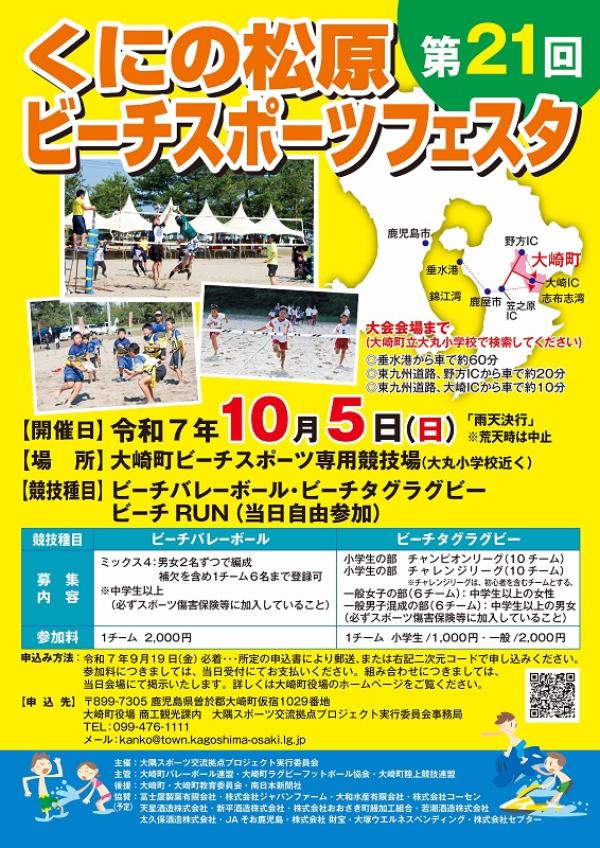
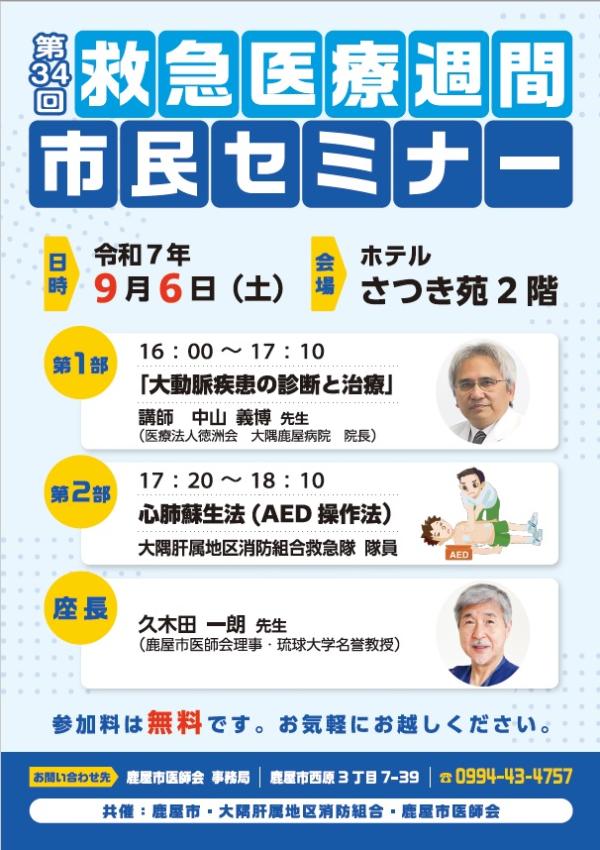

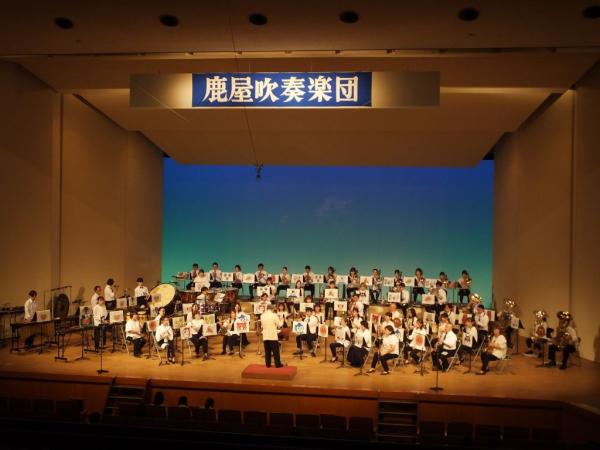

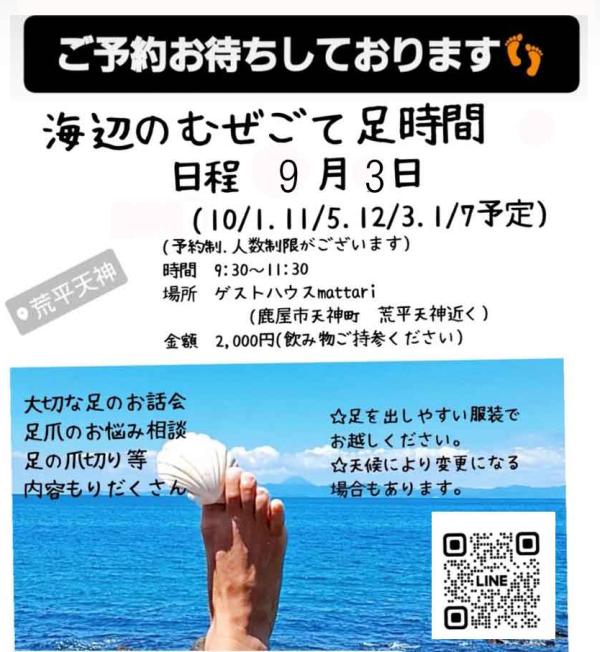



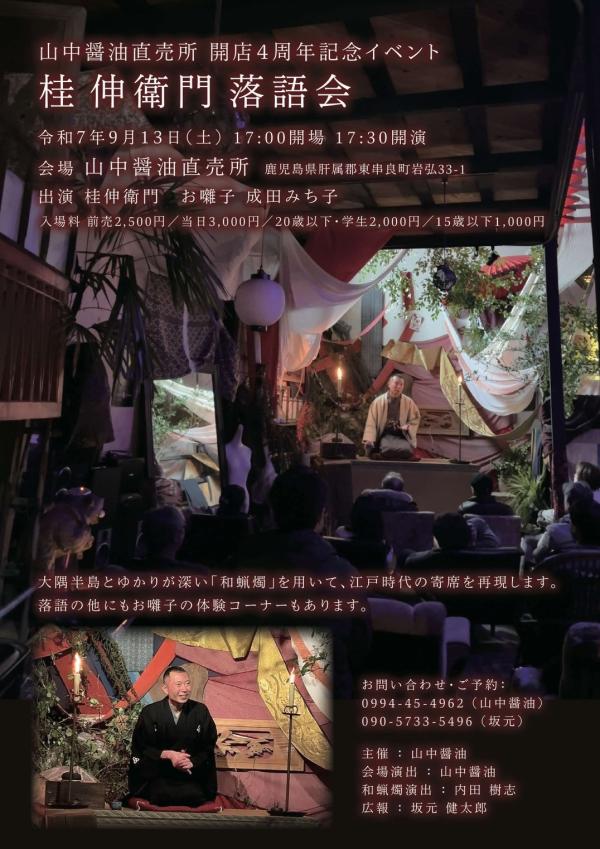
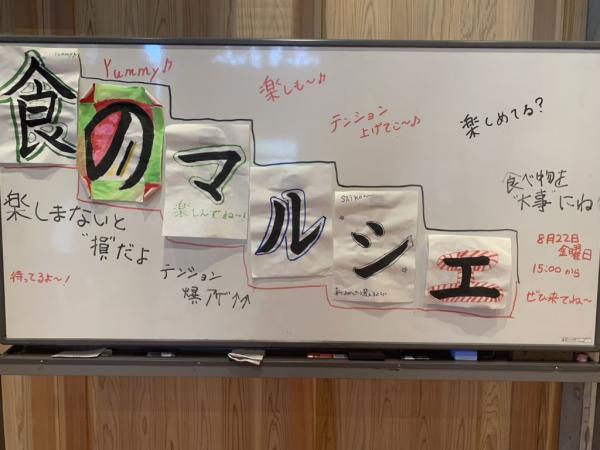


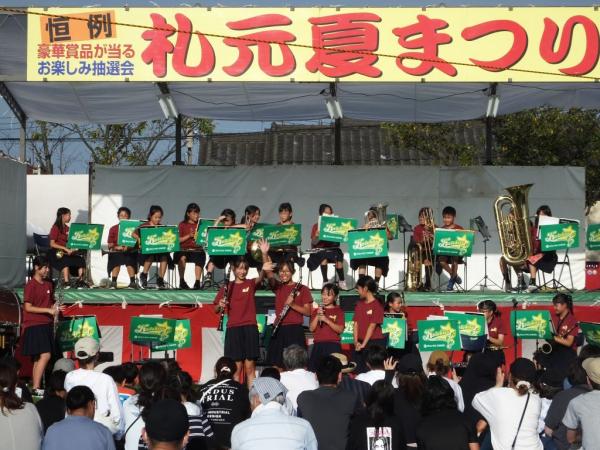
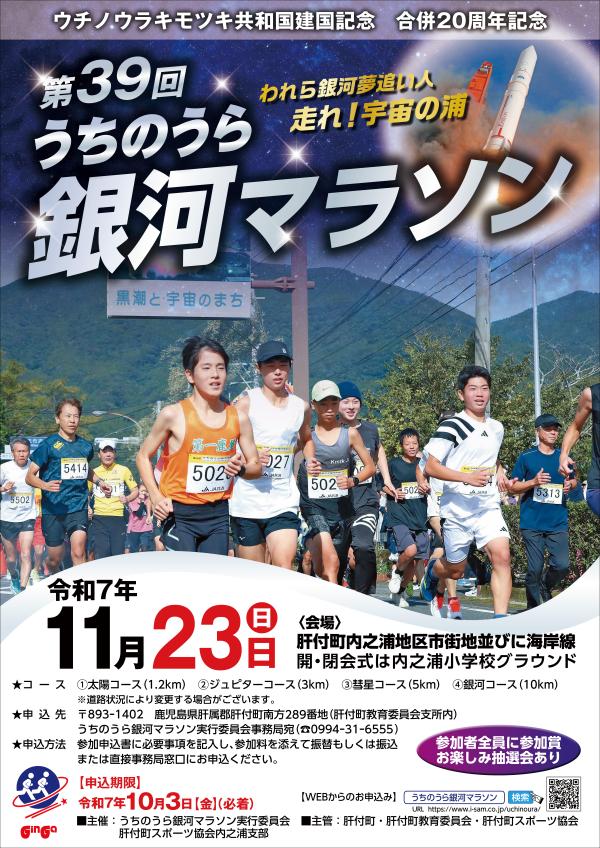












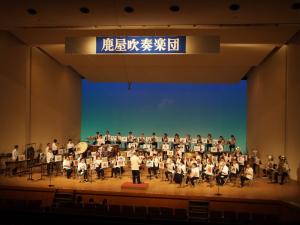


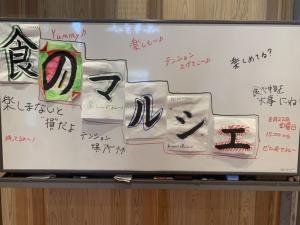












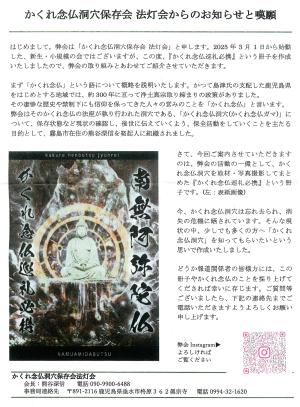







カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)