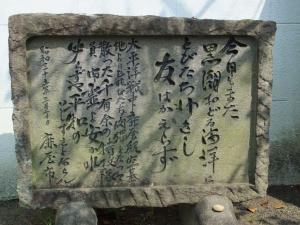《雑草(コラム) 》
令和のコメ騒動 中山間地の多い大隅半島で考えること
鈴木憲和農水大臣は、令和のおコメ騒動を受けての前政権の増産方針を見直しし、需給の均衡をはかった上で、海外への輸出や米粉の市場拡大など中長期的な視野に立ち米の需要を高めていくなどの方向性を示し、おこめ券配布を、納得感ある形で進めたい…としている。
昨今のお米の問題、まずは、スーパーなど店頭からお米が無くなったということからスタート。
日本の主食であるお米は、これまでの転作奨励や流通システムの問題、後継者不足など政策の結果で、とても不安定な食物となりつつある。
前政権では、消費者の立場をも考えて備蓄米を放出し、5㌔2000円台のお米が店頭に出て、食べる側としてはありがたい流れが出来た。
その反動なのか、2025年産米の概算金は、60㌔当たり2万6000~3万円が中心で、前年産比6~8割高。商系業者の調達競争が過熱する中で、過去最高額を示した産地が多いという。

農水省によると、10月19日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は前の週より109円高い5キロあたり4251円。5週間ぶりの値上がりで、5月中旬に記録した最高値の4285円に迫っている。
JA等が生産者に前払いする概算金が去年より大幅に上昇するなかで、価格の高い銘柄米の販売量が増え61円高い4501円となり、平均価格を押し上げているという。
「需給の均衡をはかった上」でとは?
新米と言えども、ここまで高くなると消費者にとっては、ただでさえ物価高が続いている中で、家計への影響は大きい。
新米でなく2024年産米を買い求める買い物客も多いと聞いた。
全国の情報、お米どころの情報とを考えると、今後、私たちは安心してお米を口にすることができるのか不安になる。
新米集荷めぐる市場の過熱が止まず、商系業者の声では60kg3万5000円台の攻防戦という情報がある一方で、総合的にみて需給は緩む方向にあり、暴落リスクもあるという。
なので大臣の言う「需給の均衡をはかった上」でということなのだろうか。
お米どころや、大消費地での議論と異なるベクトルで
ただ思うのは、新潟や秋田、北海道などのお米どころや、東京などの大消費地での議論と、中山間地の多い地方とのお米づくりや農業に対する考え方、方法論はちょっと違うような気もしている。
米作り含め農業が語られるとき、大規模農業化や機械化、ドローンなど利用したスマート農業による現状の打破がよく言われる。
産業としての農業を国や自治体が農業関連団体が守っていくことは、とても大事なことで、大いに進め、食の課題を解決してほしいと思う。
そうした大きな括りで農業を考えるとき場合と、ここ10年来、農業という観点もだが、私たちが毎日口にする「食」という面から、大隅半島の農というものを考え、取材し、時には合間を見て援農をしたりしている。
2009年10月にNPO大隅照葉樹原生林の会を設立し、それ以前から大隅半島の自然の豊かさを感じ活動してきて、その後、無農薬や有機でのお米や野菜作りにもそれなりに関わってきた。
大隅半島の山を中心にガイドが出来るくらい、豊かな自然と関わってきて、その豊かさを自分の健康や命に落とし込んで生活していく、そういうことが出来たら、自分の幸福度がアップしていくのではないか。
そういう観点で、「業」としての「農」ではなく、命を育む「食」としての「農」を考えて活動している人たちは、どんどん周りに増えてきている。
「農」を「食べる側」の視点で考えてみると違った景色が
そして最近では特に、子どもたちの健康のためにオーガニックな食材を求めるファミリーも増え、オーガニックマーケットなどのイベントには多くの人たちが集う。
最近、度あるごとに伝えていることだが、「農」を「産業」として捉えていく考え方、収量を得るために化学肥料や農薬等を使った、今の慣行農業が主流になっていて、これはとても大事なことだが、これらに加えて、「農」を「消費者」「食べる側」からの視点で考えてみる。
今、国も、緑の食糧システム戦略で有機食材含め、循環型食糧システムの構築を進めているが、例えば、こうした令和のコメ騒動などが起こると、話の方向がどちらかというと、海外への輸出や米粉の市場拡大などに向いてしまい、足元に光が当てられなくなる。
今、人口減少社会で、人やパイの取り合いをしていては、日本全体はよくならない…という人もいるが、「農」に関しては、大規模農業化や機械化、ドローンなど利用したスマート農業など慣行農業一辺倒ではなく、特に中山間地域では、循環型食糧システムの構築を、地域を挙げて実践しているところと、そうでないところとでは、ますます差がついてしまい、人の流れにも大きな差がついてしまう…、そういった時代になりつつあるのではとも思う。
現に、自分たちの食べるものを中心に、安心安全な食材を自分たちの手で作っている動きが、今は小さい動きかもしれないが、広がりを見せ、これが耕作放棄地解消や、農や地域の自然に向き合うファミリーが増え、地域の活気にも繋がっている。
冬場雪に埋もれる寒冷地でなく、ほぼ一年中太陽が降り注ぎ、豊かな自然に囲まれているこの地域だからこそ、「業」としての「農」に加えて、身近な「食」の観点から地域の資源というものを考え直し、この地域の強みは何なのか…「国益」もだが、その地方独自の安定した「地域益」も併せ考えてみることも大事なのか…。(米永20251027)









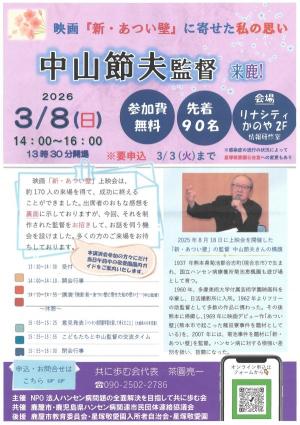

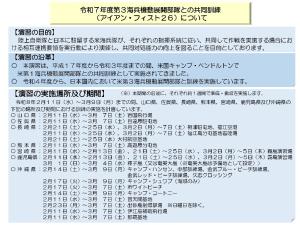


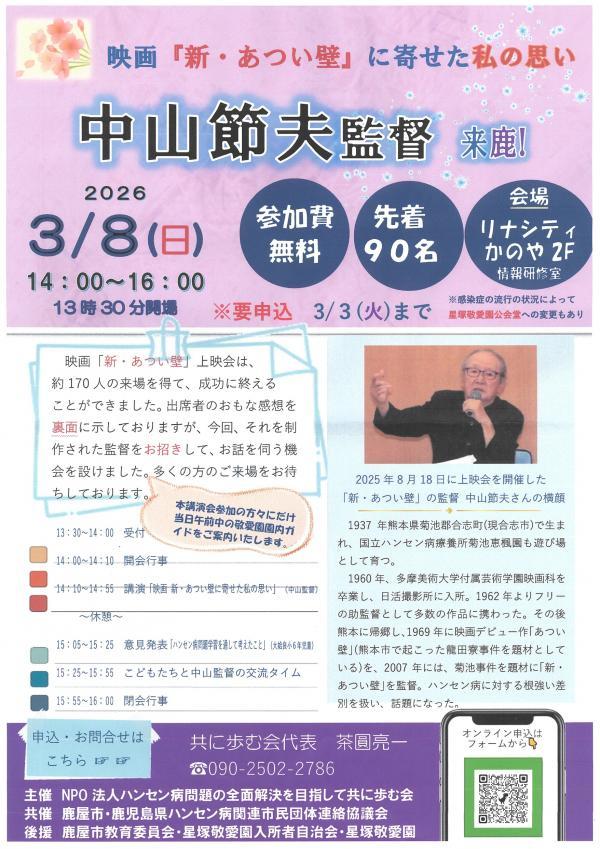













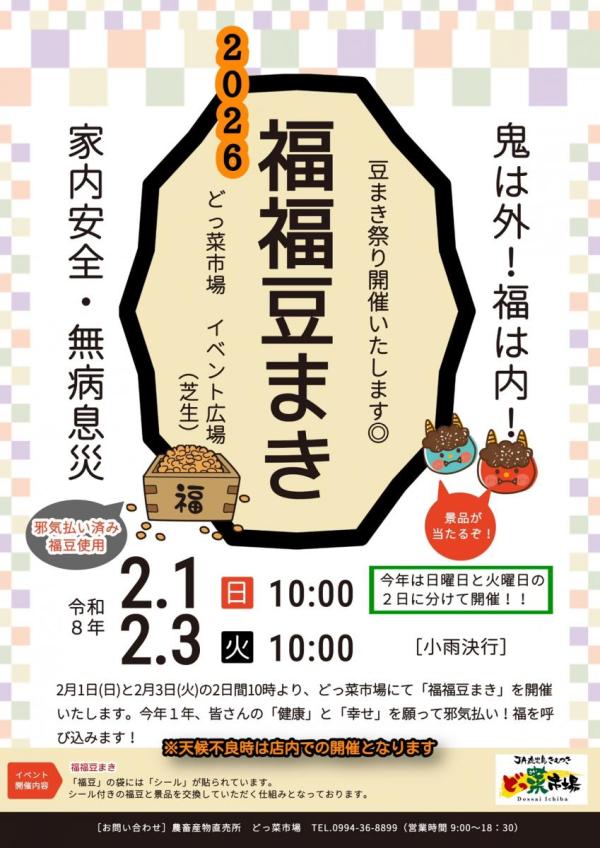







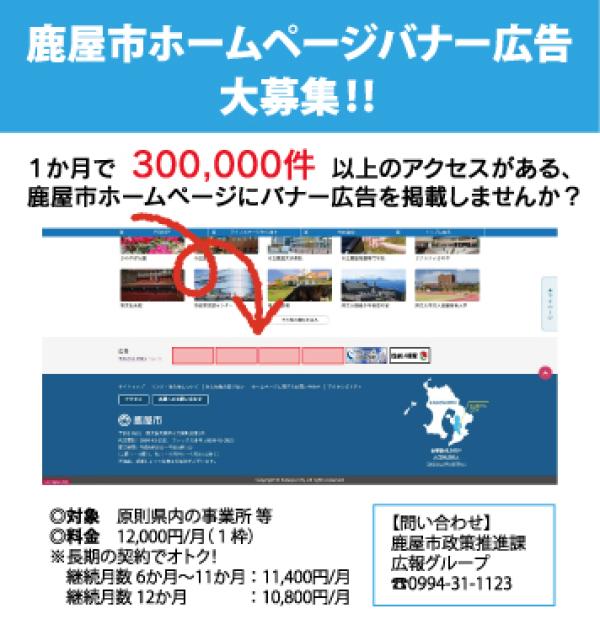
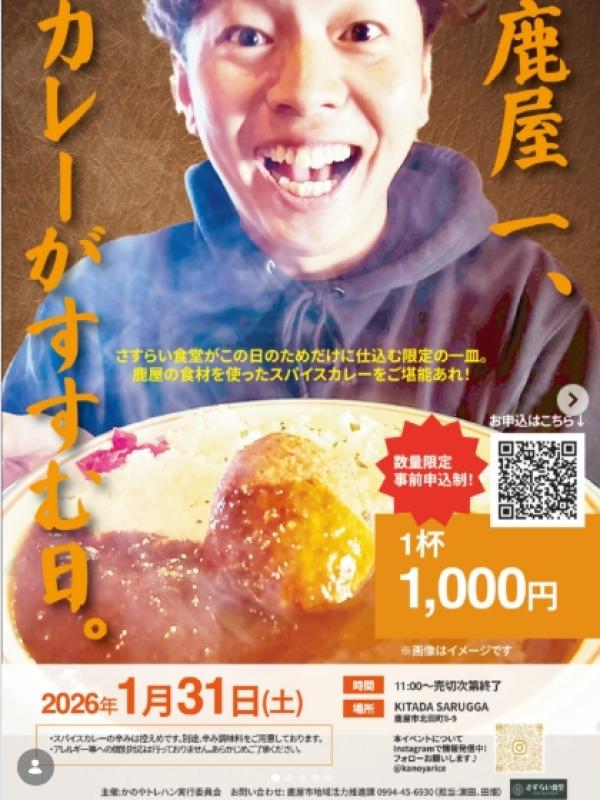




























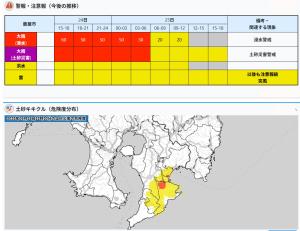









カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)