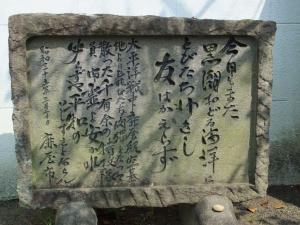《芸術・芸能 》
日本遺産にも認定された石見神楽の世界を堪能
島根県江津市との自治体間連携協定事業 石見神楽公演が、令和7年11月8日(土)東串良町総合体育館で開催され、日本遺産にも認定された石見神楽の世界を堪能した。

島根県西部で受け継がれている伝統芸能、石見神楽。
豪華絢爛な衣装に身を包んだ荘厳な舞と、勇壮な太鼓の響き。神々の物語を華やかに描いた迫力満点のステージ。
昨年、東串良町と島根県江津市との自治体間連携協定1周年記念で初公演となり大好評。
今年も江津市および江津市石見神楽連絡協議会の協力のもと実現したもの。


島根県西部石見(いわみ)地域に伝承される石見神楽は、日本神話を題材に、独特の哀愁あふれる笛の音、活気溢れる太鼓難子に合わせて、金糸銀糸を織り込んだ豪華約爛な衣裳と表情豊かな面を身につけて演じられる伝統芸能。
昔より地域の娯楽として秋祭り例祭の前夜祭として舞われるものだったが、現在では定期公演など、年間を通じて石見各地で石見神楽を観ることができるようになっている。
その演目は、厳かな雰囲気の年で神様をお迎えする「儀式舞」や、古事記や日本書紀を題材にした「能舞」など合わせて約30種類にのぼり、受け継ぐ団体は現在130を超えるほどある。
石見神楽は、大蛇が火や煙を吹くといったリアルな演出や勧善懲悪といった分かりやすいストーリーが特徴で、初めて観る人にも明快で、自すと目の前で繰リ広げられる神話の世界に誘われる。



この日の演目は天神、頼政、恵比寿、大蛇
そのあらすじは次の通り。
天神(てんじん)
平安の頃、右大臣であった菅原道真は、左大臣 藤原時平に謀られ、筑紫太宰府へ左遷されます。
その後、時平は39歳の若さで死に、その一竟も次々に死んでしまいます。
これは道真のしわぎであると考えられ、神楽では遠真が時平と戦うよう創作してあります。
石見神楽ではしい太刀対決が繰り広げられ、見わず手に汗握る展開に。
衣裳も2回も3回も早変わりして、終盤に向かうほど華々しくくなる見所満載の演目。
地域によっては随身も道真と共に激しく戦います。





頼政(よりまさ)
この神楽は、源頼政が鵺という怪物を退治するお話です。
平安時代末期、毎夜丑の刻になるとヒョ~ヒョ~と気味の悪いうねりと共に東三条の森から黒雲がわき出て、帝の寝所である厰を黒く覆ってしまいます。
帝はそのたびにうなされ、ついには病魔に侵されてしまいました。それは、姿のわからぬ鵺という怪物のしわざ。
天皇は、弓の名手である源頼政に鵺退治を命じ、頼政は家来の猪早と共に森へ向かいます。逆中いたずらをする猿たちをこらしめ、いよいよ鷸も登場。無事に込治することができました。







恵比寿(えびす)
この神楽は、出雲の国美保神社の御祭神、恵比寿様が磯辺で釣りをしている御姿を舞ったものです。にこやかに第を釣る恵比須様の様子が面白おかしく、心の和む演目。
恵比須様は昔から漁業、商業の神様として崇拝されています。




大蛇(おろち)
その昔、天照大御神の弟である須佐之男命の悪行により天照大御神は天の岩戸にお隠れになり、須佐之男命は天高原を追われます。
諸国を歩くこととなった須佐之男命が、出雲の国斐川にさしかかると嘆き悲しむ老夫婦と娘に出会います。
理由を尋ねると「私共夫婦は八人の娘をもっていたが、この地方に住む八岐の大蛇に毎年一人ずつ娘をさらわれ残るはこの娘一人となった。今年もそろそろ大蛇が来る頃になったので嘆き悲しんでいる」とのこと。
須佐之男命は、大蛇退治の為、老夫婦に濃い酒を作る事を命じ、やがて現れた大蛇がこの酒に酔い伏せたところを退治するという神楽です。














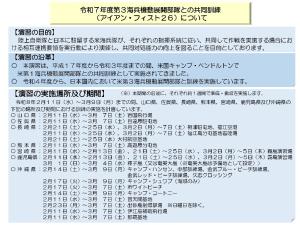












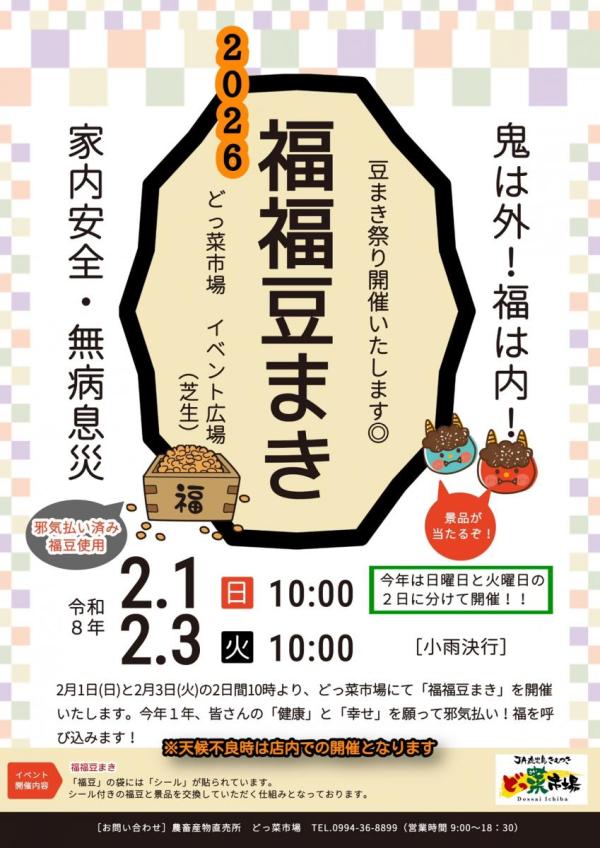








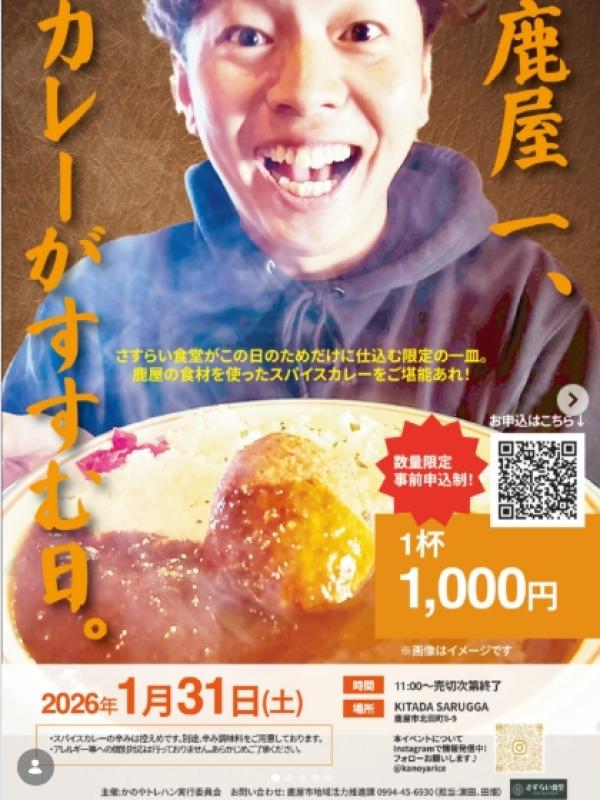


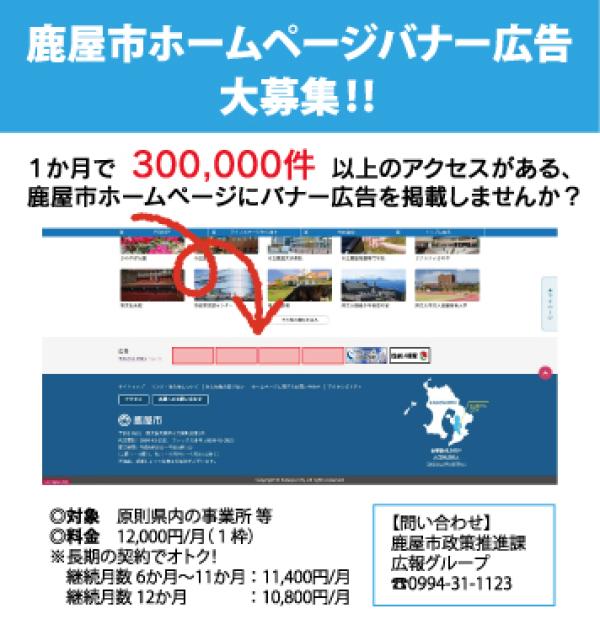





























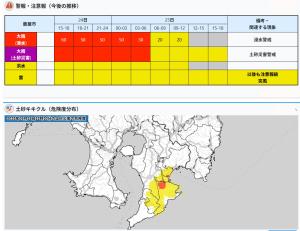









カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)