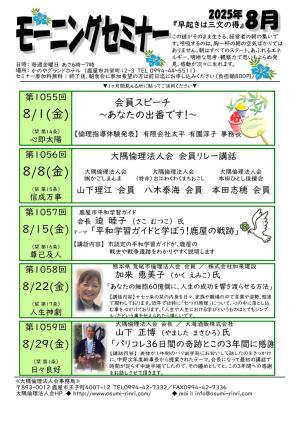《雑草(コラム) 》
作る側の視点からと、食べる側の視点からと農を考え…
最近はまた、食に関しての情報に接する機会が増えてきた。
10年くらい前も、大隅半島の食や自然の豊かさを何らかの形で伝えることが出来たら…と、食に関する情報を収集していた。
ただ今回は、自分のことも含めて、身体にいい食材や、今の自分の体調に合わせた食事を気にしながらで、そんな情報に耳が大きくなってきている、個人的なことが主で…。
なので有機や自然栽培ということにも興味を持って、そうした現場にも足を運んだりし、今、自分たちが食べている野菜、食材についていろいろ意識しだしてきて、よりヘルシーなものを求めるようになってきた。

そんなことをしていると、例えば、いま普段買って食べている野菜の中には、ほおっておくと溶けて黒っぽい水になり、臭さもあるものがある。
有機栽培等で畑からもらってきた野菜はそうならない…、その差は何なのか、私たちは何を食べているのだろうと考えることがある。
さらには、薬草や薬膳等にも興味がわき、いろんな情報に接しているが、それが毎日の食生活にはまだ繋がってこない…。
この歳になると、同級生と顔を合わせても、しばらくすると健康の話になる。
私の場合、若い時の暴飲暴食、とくに呑むほうが激しかったのか、あちこち具合がよくない。この歳ですこぶる元気でどこも悪くないという人が珍しいのだろうが、もっと元気でいたいと思うこのごろ。
思うのは、不老長寿とまでは言わないが、2024年の健康寿命は、男性が72.57歳、女性が75.45歳らしく、もっと元気な年配の方々はまだいっぱいいらっしゃる、そうした仲間入りしたい…、皆が願うことだろうが…。
食の多様性ももっと考えてみる
ただ、鹿児島、この大隅半島は食の宝庫だとも言われるが、いいものがまだまだ眠っているような気もする。ここ最近になってトリゴネリンとか、ポリフェノールなどによる抗酸化能とかを、食材を通じて教えてもらうようになった。まだまだ理解は浅いが…。
これは何も、今の慣行農業についてどうたら…というわけでなく、社に届くいろんな資料をみていると、スマート農業技術等の開発・改良、そうした企業の実証例などが紹介され、皆さん頑張っておられる。
ただ中山間地域での耕作放棄地問題や、自分で食べる分は自分で作るというファミリーも増えてきているようで、そうした人たちに関しては、有機や薬膳、機能性食品や抗酸化能などで食材を考えてみてもいいし、食の多様性まで考える人たちが広がってくると、よりヘルシーで健康寿命も延びる地域になってくるし、それが医療費削減などにも繋がっていくのだろう。
最近は、地域のお米農家とも話しをさせてもらうこともあるが、田植をする前から注文が舞い込んできて、対応が大変という。
お米はいつも知り合いなどから籾で買い、玄米で食べていることが多いので、市販のお米がどれくらい高くなっているのかよくわからないが、確かに高くなっていると思うし、ただ、それが本当に農家へ還元されているのだろうか…、いろんなところにストックされたままで動いていない…と耳にしたりする。
スーパー等では、外米と国産米とのブレンド米が売られ、国産米もどこどこ産というものがほとんどなく複数原料米として販売されている。
農と食というものを根本から考え直すときなのか…
以前も書いたことがあるが、慣行農業やスマート農業は、作る側の視点から農を考え、有機や自然農は、食べる側からの視点から農を考え、それらを地域の中でしっかり棲み分けして、バランスをとりながら農というものを根本から考え直す必要に迫られているのではないか。
食料・農業・農村基本法が、平成11年の制定以来初めて令和6年5月に改正され1年が経とうとするが、もっと食べる側からの視点で農業を考えていくと、違うスタイルでの農も考えることができるし、それが人を動かし、耕作放棄地や後継者不足解消の糸口になったりやしないか。
作る側も消費する側も、そういった考えの人たちがもっと増えてくると、地域の元気にも繋がっていくのでは…、私の元気にも繋げたい…。(米永20250514)











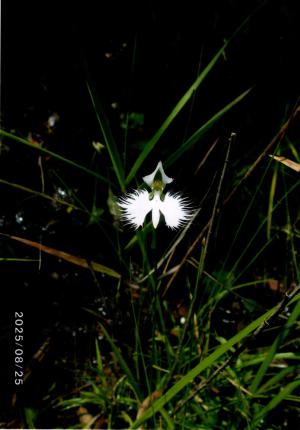
_(説明資料)滞空型UAV(シーガーディアン)の鹿屋航空基地への配備について_00002.jpg)







_00003.jpg)









_00002.jpg)








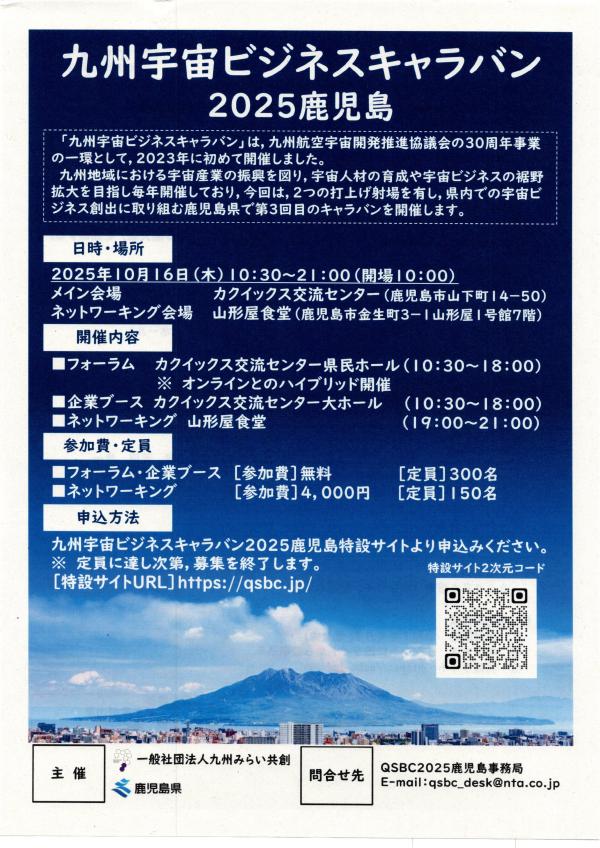




_00003.jpg)







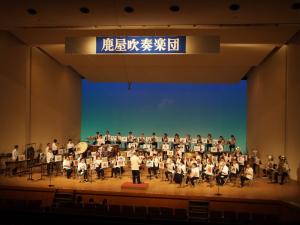















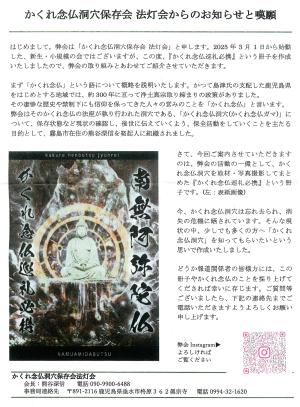







カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)