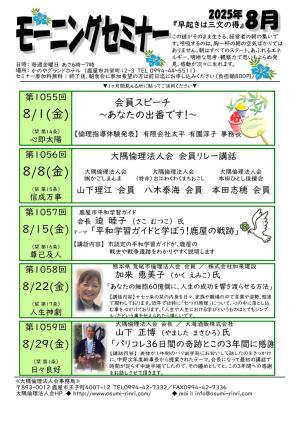《雑草(コラム) 》
流通 そして後継者不在の現状 苦しいコメ農家の元凶は…
続いてお米の話題…。
会員制量販店だが「コストコ」で備蓄米の販売が始まり値段も10キロで税込3480円だという。
備蓄米は2022年産の「古古米」で、複数の原料米をブレンドしたもの。
5キロあたりの平均価格が、先週に比べて256円値下がりし3920円という中での、10キロ税込3480円という価格。
買い物客は、通常10キロ4000台の時、セールなど安い時の価格と同じ値段だ…と手に取っていったという。
また小泉農相は25日、石川県輪島市を訪れ、備蓄米販売店を視察。
2021年産「てんたかく」が5キロ1800円だったというので、だいぶ安く店頭に出ているようだ。

お米流通に関しては、農水省が米流通の7万事業者のすべて在庫を確認。
小泉農相は、概算金変更をJAグループに要請し、JAは農家からコメ直接買い取り、全中と認識一致…などのニュースが流れている。
農水省がJAや卸売業者に対してアクションを掛けており、それなりの動きがあると思うが、それにしても7万事業者というのは、在庫の報告があったとしても、それを実際確認する作業は、大きな労力が必要なのだろう。
遡ると、米穀配給通帳による指定の米穀店で米を購入する配給制の時代。
1969年、ヤミ米の増加などを受けて、一部で国を通さない流通を認める自主流通米制度が導入され民間流通が本格化。
1990年からは自主流通米の入札が始まり、価格形成センターの入札価格が米価指標に。
1995年まで続いた食管法時代までは、国が米の流通を管理していたという歴史。
同年11月に食糧法が施行され流通規制が大幅に緩和され、国の役割は備蓄の運営などに限定された。
そして2004年には食糧法が改正され米の流通がほぼ自由になり、米卸業者は仕入・販売の自由度が増す一方で競争は激化。
2006年ごろからは、国が公表する産地と卸の相対取引価格が指標になっているという。
米流通について7万事業者というが、米卸は全国に1822社、1億円未満が30.5%の555社だという。
生産者から玄米を集荷・仕入れした米卸業者は、精米・加工してニーズに合わせた商品を提供。精米された米は、スーパーマーケットや飲食店、学校、病院などに流通されるという。
特に、米の需給バランスが崩れてきた傾向のあった2024年前後から、投機目的の取引業者が増えたという情報も流れていた。
お米の生産に対する課題については少し置いておいて、やはり7万という米流通の関わる事業者数だから問題が生じてくるのではないのだろうか。
その中には、米を投機的に扱う業者も出てくるのだろう。平成、令和と続くコメ騒動を経験したが、おそらく今の制度では繰り返し繰り返し発生してくると思う。
消費者にとっては、量販店等で安く買えるケースがあり喜ばしい半面、不作等で需給バランスが崩れた場合に、米価格が乱高下する。
食料自給率が37%という中での、ほぼ100%というお米の存在。
備蓄米も含めて、食の安全保障という観点からも、なるべく混乱が起こらないよう、騒動とならないよう、流通にもある程度国が関与していくことも必要なのではとも思う。
汗水たらして開墾、苦労して水路等を引いてきた思いは…
生産者にとっても、消費者に届くまでの複雑な流通経路を経るのでなく、苦労してお米作りをしているその姿を見ていると、米農家に少しでもお金が残るシステムとその価格設定、そこには、今の補助金制度も見直し、農家に直接補償するなどの形も、お米に関しては考えてもいいのか。
先日も、近くの主婦とかのお手伝いをもらい、4町ほどお米作りをしている70代の農家とお話しして、今年は7反増やして5町になったという話を聞いてびっくり。
7反でも大変なのに…と思いつつ、あと5年経ったらどうなるのだろう、後継者は…という私たちの主食に対する不安もよぎった。
減反政策の反動が後継者不足になっているとするならば、少し思いが偏っているのかもしれない、大規模農業化もだが、中山間地での耕作放棄地解消のために何らかの助成等ができないか。そこには余計、人の問題も付きまとうのだが…
先人たちが汗水たらして開墾し、苦労して集落で山裾から水路等を引いてきたその思いや歴史が消え去ってしまう、現実にどんどん無くなっていく様を見ていると心が痛む。(米永20250627)











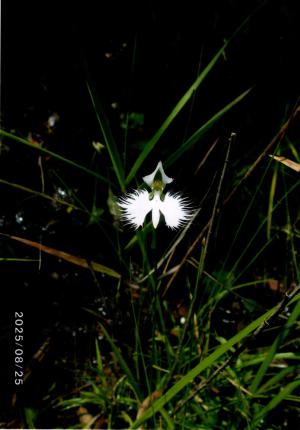
_(説明資料)滞空型UAV(シーガーディアン)の鹿屋航空基地への配備について_00002.jpg)







_00003.jpg)









_00002.jpg)








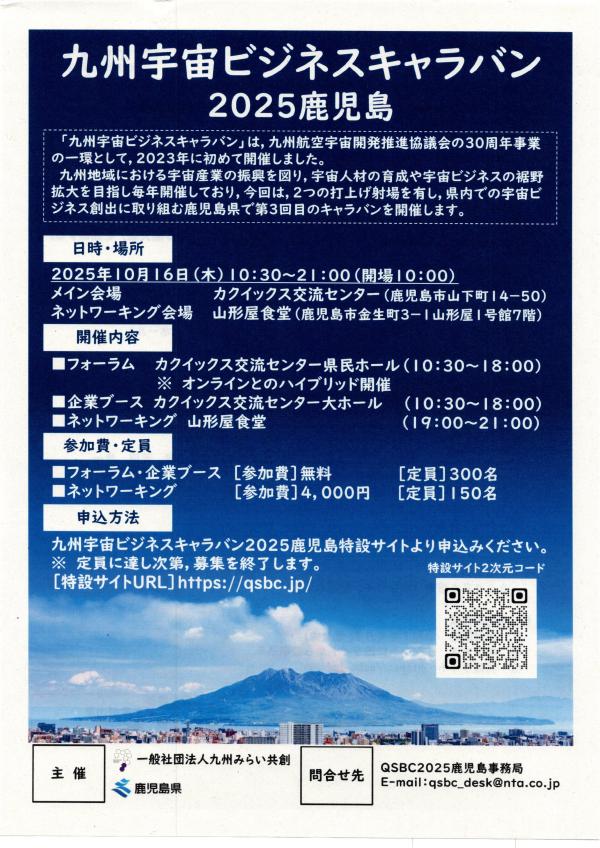




_00003.jpg)







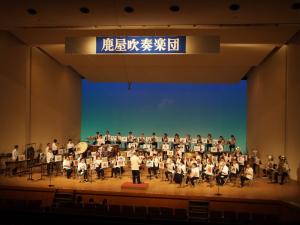















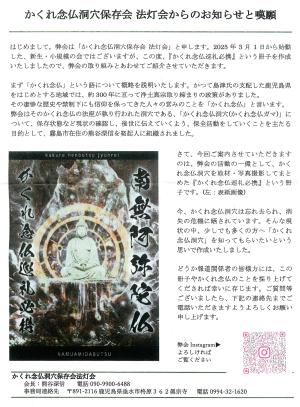







カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)