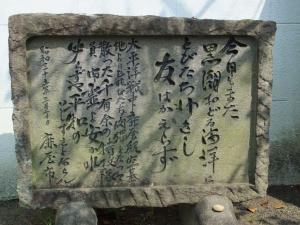《おおすみ雑記 》
農そのものを棲み分けて考えてみる
少し前は、別なコラム「雑草」で、種のことや食について書いていた。
私たちが口にする食材について、いろいろ話題になることが多くなってきたからで、若いころ、スポーツを盛んにしていたときは、肉もりもり、ビールや焼酎もかなり吞んできたが、最近は野菜が中心になり、アルコールもほどほどに、そういう歳になってきた。

なので毎日食べる野菜についてとても気になり出し、今の農業の在り方について根本から考えるようになってきた。
というより、食そのものについて本を読んだり、セミナーを聞いたりで、改めて水や太陽光、酸素のこと、遺伝子や酵素、土壌のこと、実際畑とかやってみないと分からないのだろうが、胚芽やデンプンがどんな仕組みで植物を育てていくのか、空中や地中からの養分がどんな形で植物を大きくしていくのか、とても難しいが生物科学的にも少し踏み込んでみた。
結果、今の段階では、まだぼやっとしていて答えはないのだが、パーマカルチャー的な考え方…、これらは環境配慮型、循環型、自然農、有機農、不耕起、協生農など、いろんなやり方をしている方がおられ、まだ何がいいのか、その中で、その地域に合った、自分に合った方法を模索しているようだ。そういった人たちが今、周りにかなり増えてきていると感じている。
これは、例えば、窒素リン酸カリなどを考え、化学肥料を用い、また農薬を使って、耕し、天地返しなどで毎年同じ作物をそれなりの量作っていくという慣行農法が一方であって、どっちがいいのかという議論もある。
今は慣行農法が主流で、食料の安定供給の確保のため、海外の市場の拡大などで、ドローンやITなど駆使し大規模農業へ向かうことが、食料・農業・農村基本法などで進められている。
経済的というよりライフスタイル
一方で、みどりの食料システム法では、CO2ゼロエミッション化の実現や化学農薬の使用量(リスク換算)の50%低減、化学肥料の使用量の30%低減、有機農業の取組面積の割合を25%に拡大するなど決められていて、どちらも大事なことなのだろう。
しかし、慣行農法では機械化なども含め、農業を始めたり継続していくには、それなりの投資が必要。
一方で自然農、不耕起などを実践している人たちは、自給+αで収量は少ないかもしれないが、半農半Xというような経済的というよりライフスタイルとしての農を求めている。
フィールドはいっしょだが、向かう方向は全く違うということなのだろう。
一口に農業と言っても、農作業と農産業、もっと言うと、自然の循環を生かし、最初、その土地や土に合うまでは大変だが、環境が整ってくると最終的にはあまり手をかけない農業と、手をかけて収量を考える工業的な農業。
法律では同じくくりで規定されている部分もあるが、実践する側としては、どちらかというと別個のものとして捉えたほうがいい、というより、そう考えないと、現場が混乱すると思う。
葉や根で会話し身を守る
なぜ、そういうことを考えるのかというと、最近は、植物同士が、何かが起こった時、例えば虫が食べにきたときにその葉っぱなどから出す人間にはわからない匂いで会話をし、その虫の嫌がるような毒素のようなものを出して身を守っている。
日常的にも、根っこからさらに出ている菌糸が、周りの他の植物とも地下で結びついていて、コミュニケーションを取り合っているということが、テレビ番組でのガリレオⅩやNHKスペシャル、ユーチューブなどで伝えられていて、そういうこともあって不耕起栽培を目指している人。
このほか、耕作放棄地で目立っているセイタカアワダチソウやススキが生えているところに植える野菜の種類。
それがステージ1だとすると、スギナなどの第2ステージの時は、何を植えたらいいなど、その土、土壌によって雑草の種類が決まり、雑草の根が耕してくれている、雑草を邪魔者としてでなく、それ以降も自然の摂理にあった植物の循環をうまく活用していく。
雑草も一つの循環
失敗をしながらも、うまくいくには数年かかるとも言われるが、それでも、そうした情報をもとに、田畑と向き合っている人がいるということ。
その理論が分かって農に向き合い、それがその過程の中ではまると雑草も一つの循環。今、ネットでもそうした情報があふれていて、特に鹿児島のように、雪とかに覆われないでほぼ1年じゅう作物ができるところからも、何やら発信されている。
なので慣行農法とはまた、違った感覚で接しているのだと思う。今、そういった畑を見学に行ったりしている。新たな発見だ。
国が決めた農に関しての法律は、表向きはそこを区別しているみたいだが、しかし、現実に運用していくとなると、その地域や自治体の中で混乱していて、CO2ゼロエミッション化とかなるとまだその踏み込む段階でもバラバラのようだ。
ただ、これらにいち早く気づき、どちらがいいとか悪いという議論でなく、両方ともちゃんと認め、それを棲み分けてしっかり進めていく地域や自治体があるとすれば、特に地方では活気に繋がっていくのか。そんなふうにも考えている。現実的にかなり進んでいる地域もあるようだ。
大隅半島ではまだ、一部の人たちの中で盛り上がっているだけか…。(米永20240617)









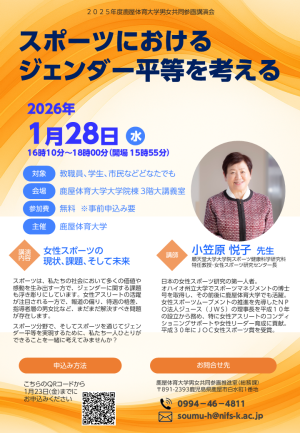




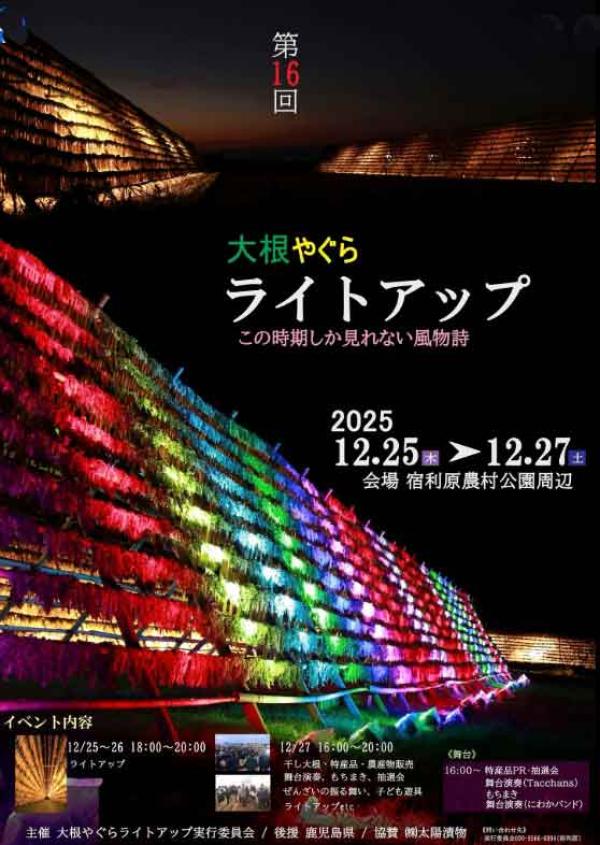
















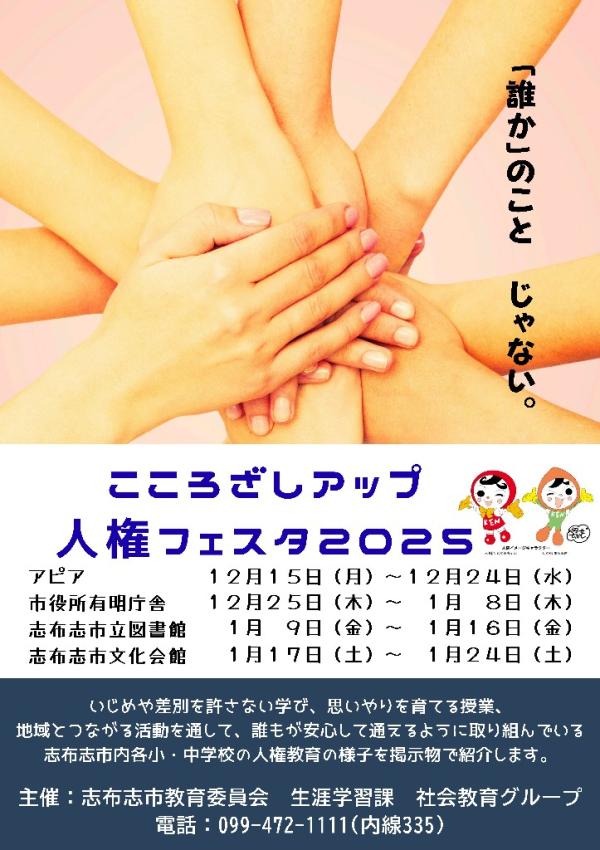
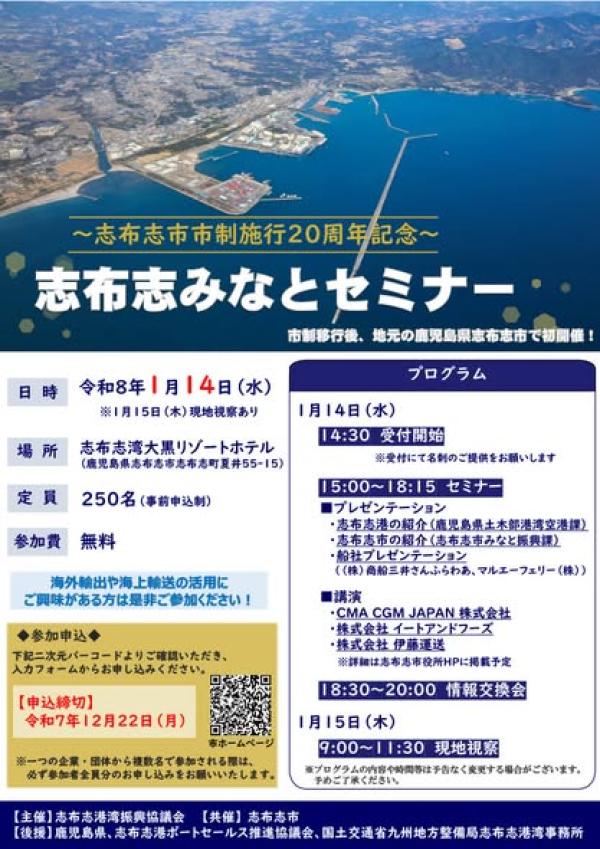




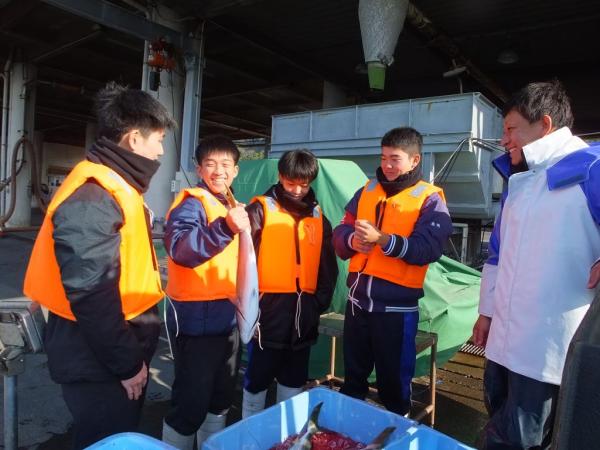

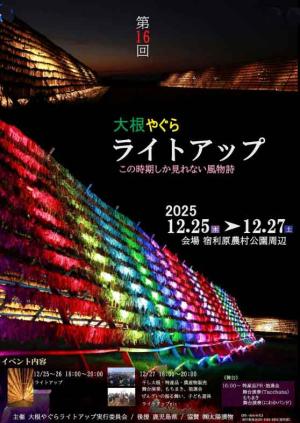
























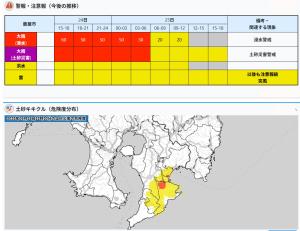






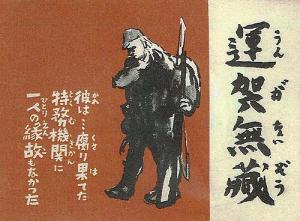



カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)