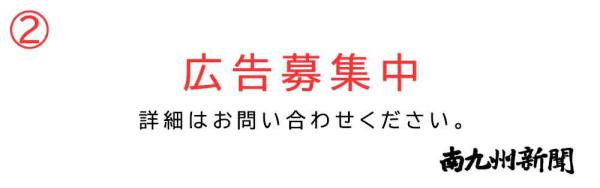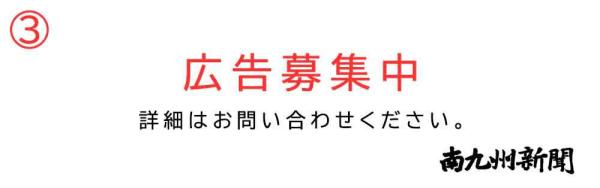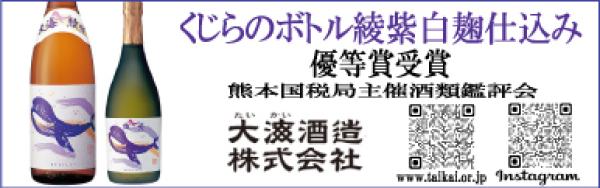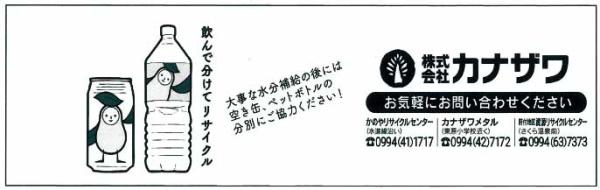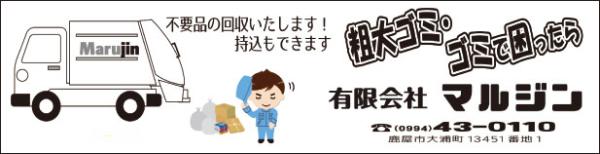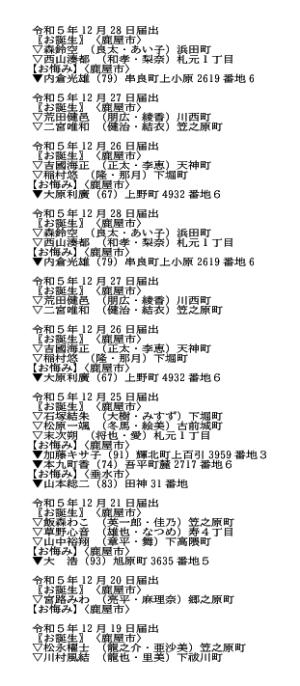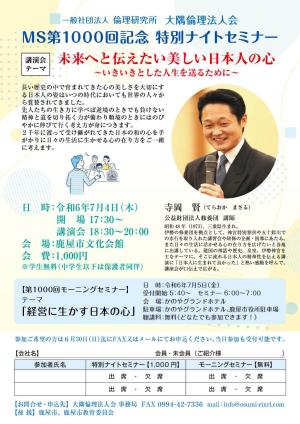《雑草 》
安保関連の大きな流れの中で考え、感じること
ここ数回、基地のあるマチに住む私たちにとって、この国の防衛、自衛隊が近い将来どうなっていくのかがとても気になるところであり、分かる範囲で書いてきた。

写真=Official Seal of Valiant Shield HPから
特攻基地のあったマチだからこそ、敗戦後の鹿屋市、日本の姿をいろんな文献に目を通したりし、進駐軍の鹿屋市金浜上陸のこと、当時の永田良吉市長との日本の歴史的にも特筆されるような出来事など、少し深堀してみたりした。
そして、だいぶ前の話になるが、開隊40周年でエアメモが始まったころは、自衛隊の方々とかなり交流をさせていただいて、一方でこの国を守る…ということを考える共有した時間もあった。
ただ時代は大きく様変わりした。
その当時は、海自の主要基地の中で、米軍が併設されず残されている鹿屋基地でもあり、日本人として日本という国を守るための最後の砦なのか…という勝手な思い込みもしていた。
しかし、この鹿屋基地でも米軍の訓練の場となって、法改正や自衛隊に関する解釈に大きな変化があり、沖縄だけでなく九州が防衛力強化の最前線に立たされている。
八戸や松島基地でも米軍の戦闘機が展開し訓練
加えて来月には、太平洋地域で2年に一度行われているアメリカ軍の大規模演習が初めて、日本でも行われることになる。
米軍は、陸海空軍や海兵隊など1万人以上が参加する大規模な実動演習「バリアント・シールド」を2年に一度、グアムなどで行っているが、今年の6月上旬から約2週間の日程で、在日アメリカ軍基地のほか、青森県の海上自衛隊八戸航空基地や、宮城県の航空自衛隊松島基地にもアメリカ軍の戦闘機が展開して、周辺の空域で航空自衛隊とともに訓練を行うことなどが計画されているという。
海自八戸航空基地や空自松島基地では自衛隊の哨戒機や戦闘機などが配備されているが、米軍の戦闘機の訓練が行われるのは異例であるとされ、南西諸島を中心にとした訓練が、全国にしかも陸海空と広がり、そこへ自衛隊が参加していくというケースがこれからも増えていくのだろう。
周辺で有事が起きた場合の即応体制を強化する狙いなどがあるという。
今国会で成立を目指す地方自治法改正案で何が…
鹿屋基地に米軍が関わるようになる過程で、行政に対しても、それら協定が締結される時に、文書化するのはできないにしても、「沖縄基地の負担軽減を」というメッセージを出したり、こういった機会だからこそ、地位協定について言及できなかったのかと伝えたことがあったが、そういうレベルではなくなってきているようだ。
それは、集団的自衛権が認められ、安保三文書が閣議決定され、そして今回、国会で審議中で今国会で成立を目指しているという地方自治法改正案。
非常時に国が自治体に対して「必要な措置」を指示できる権限が盛り込まれている。
政府が3月1日に閣議決定し国会に提出したものだが、現在の国の指示権は、災害対策基本法や感染症法など、個別の法律に規定があれば発動が可能となっているものの、この改正案では、大規模災害や感染症のまん延など国民に重大な影響を及ぼす非常事態で、個別法に規定がなくても、生命保護に必要な措置の実施を国が自治体に指示できるようにするものだ。
「指示権発動に、立法府は蚊帳の外でいいのか」や、国と地方の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に改めた地方分権改革に逆行するなどの批判がある中で、これもほぼ国民の多くが、こうしたこの国のかたちを変えていくような重大な内容を知らぬままで法改正される方向に進んでいる。
これらについて政府は、コロナ禍において国と自治体間の調整・連携が不十分だったことを指示権の範囲を拡大する理由としている。
自治体の自治事務全般に対して網羅的に指示権…?
この事例については賛否があるのだろうが、例えば、辺野古新基地建設問題においては、政府が沖縄県の方針や県民の意思とは別なかたち「代執行」によって知事の設計変更の承認権限を越え工事を強行している。
この法改正で指示権の拡大によって今後、政府による自治体への介入が増幅していくのではという懸念も指摘されている。
話を安保問題に戻し、現行有事法制下では、国が自治体の対処措置に是正の指示を行えるのは、国民保護法による避難・誘導・救援と特定公共施設利用法による港湾・空港の利用に限定されている。
しかし、同改正案では、武力攻撃事態にあってはもちろんのこと、武力攻撃予測事態の認定すらできない段階であっても、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が「発生するおそれがある場合」と判断されれば、国が指示権を行使できる上、一般法である地方自治法を根拠として、自治体の自治事務全般に対して網羅的に指示権を行使することも可能となる。
「この国のかたち」、歴史の探究に向かわせたもの
話が飛躍し過ぎるかもしれないし的外れだと言わるのだろうが、安保関連のこれらの大きな流れを見てみて、ふと思い出したのが、以前も書いたことがある司馬遼太郎の「この国のかたち」全6巻の中の第4巻での「統帥権」という言葉。
これも賛否様々あると思うが、書評には次の内容が記されている。
昭和前期、日本を滅亡の淵にまで追い込んだ軍部の暴走の影には、「統帥権」という魔物がいた。国家行為としての「無法時代」ともいうべきそのころの本質の唯一なものが「統帥権」にあると気がついたのは、『この国のかたち』を書いたおかげである――この国の行く末を最後まで案じ続けた作家が、無数の歴史的事実から、日本人の本質を抽出し、未来への真の指針を探る思索のエッセンス。
司馬遼太郎は敗戦を経験しており、なぜ日本という国が無謀な戦争に突き進み自ら破滅の道を選んだのか、このどうしても解せない疑問を解決したいとの思いが、彼を歴史の探究に向かわせた。
これらと今の流れを重ねるわけにはいかないが、ただこの本を読みこんでいくと、何か心に響くものがある。
この限られたコラムの中では、しっかりその内容を伝えられないが、特攻もも含めた鹿屋基地の歴史と戦争の歴史をさらに学んでいくこと、今のこの時代の流れを掴んでいく一つの何かしらヒントにはなるのかもしれない。
くどいようだが、基地のあるマチに住む一人として考え、伝えたいこと…(米永20240524)