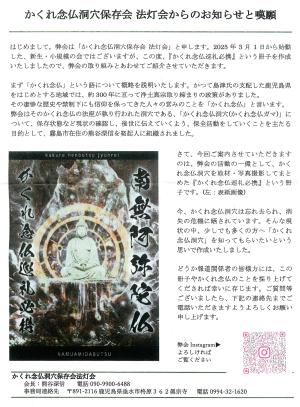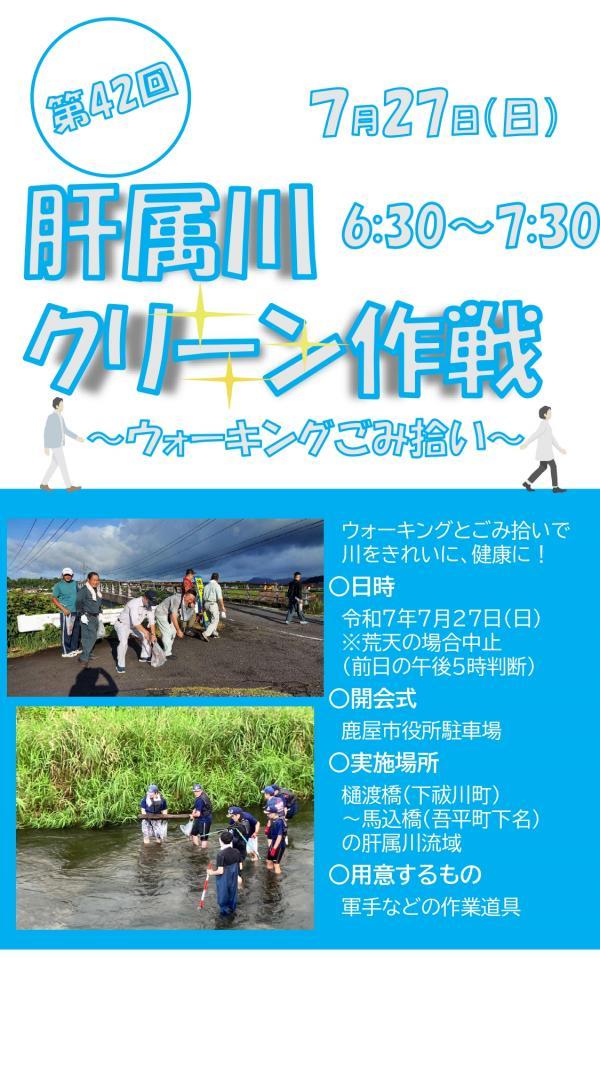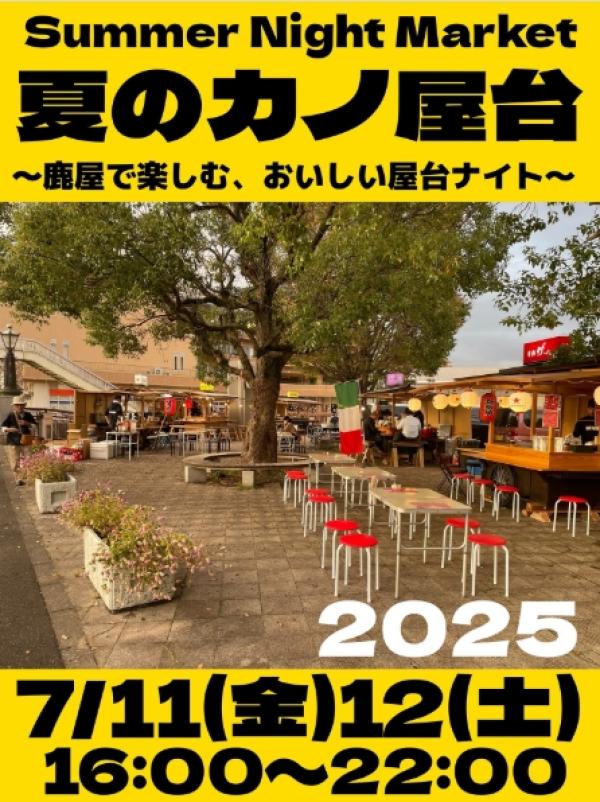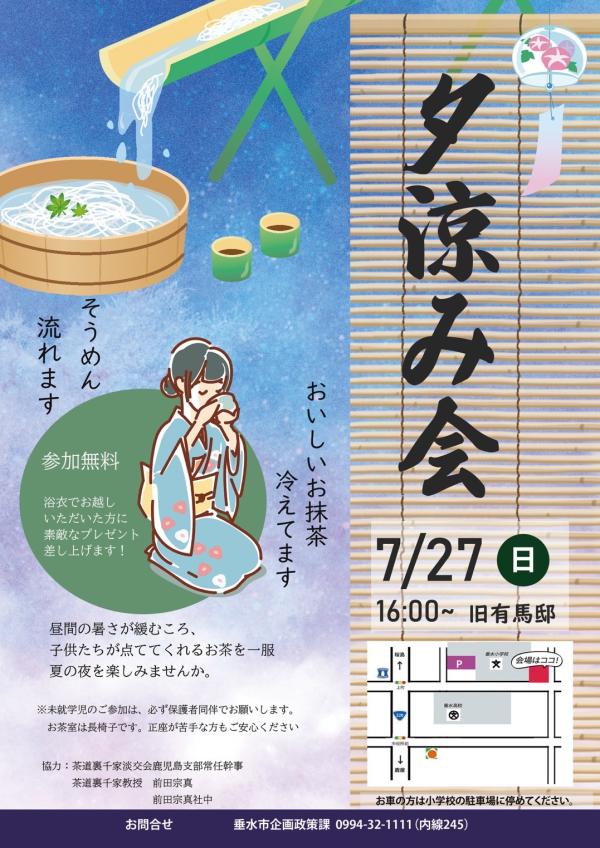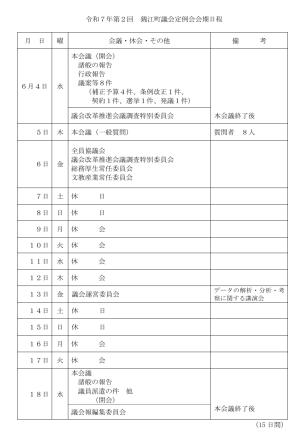《食・物産 》
職員らが美味しいお茶に親しむ~大隅地域のお茶を学ぶ会
大隅地域のお茶を学ぶ会が、令和7年7月3日、大隅地域振興局別館で開催され、職員らが荒茶生産量が日本一となった鹿児島茶の知識を学び、美味しい淹れ方などを体験し、鹿児島茶に親しんだ。

鹿児島県の産荒茶生産量が令和6年産で初めて日本一になり、大隅地域は、県全体の荒茶生産量の25%を占めていて煎茶をはじめ、玉露やてん茶、ウーロン茶や紅茶など多様な茶種を製造する本県の主要産地となっている。
一方、リーフ茶の消費は減少しかごしま茶の県内外における認知度も低い。
このため振興局の職員自らが地域のお茶に対する理解を深め様々な場でPRすることでかごしま茶の認知度向上や消費拡大に繋げていくことを目的に実施され、地域で丹精込めて作られた茶の生産概要や、お茶の美味しい淹れ方などについて学び美味しくいただいた。


この日は、会場に水出し茶や紅茶の試飲もあり、坂脇健一大隅地域振興局長があいさつ。
濱崎正樹農林水産部技術補佐兼茶普及係長が、大隅地域の茶の生産概要やお茶の種類及び成分と効能、お茶ができるまでまでなどを説明。
お茶の淹れ方についても説明があり、実際体験し、お茶の香りを楽しんで急須にお湯を注いで、大隅産のお茶を試飲した。


鹿児島県の茶は、令和6年度に荒茶生産量が27000トンで、静岡県の25800を抜いて日本一に。
(公社)鹿児島県茶業会議所が定めた規格基準(かごしま標章茶規格基準)に合格したものだけが、かごしま茶シンボルマーク貼付けすることが許可され販売。。
かごしま標章茶規格基準は、外観や香り、味、色が、販売価格に見合った品質であるかなど審査項目があり、これらの厳しい審査により高品質のお茶を提供している。
不発酵茶としての緑茶は蒸し製と釜炒り製、半発酵茶のウーロン茶、発酵茶の紅茶の種類があること。
お茶に含まれる成分と味の成分、タンパク質(アミノ酸類)は旨味成分、タンニン(カテキン)は渋味成分、微量成分カフェインは苦味成分など。
お茶が出来るまでの工程なども説明があった。



また、お茶の風味は,お湯の温度と濃度により異なり、自分好みのお茶を探しましよう…と、一人分ティースプーン1杯約2g茶葉を急須に入れ、約1分の浸出(時間が長いと濃くなる)。①→②→③ ③→②→①と湯呑みに均等につぎ分け、熱湯と湯冷ましによるお湯の温度の違いでも飲み比べも行い、それぞれ感想を述べていた。
海外向け「かごしま茶」紹介 You Tube動画総集編