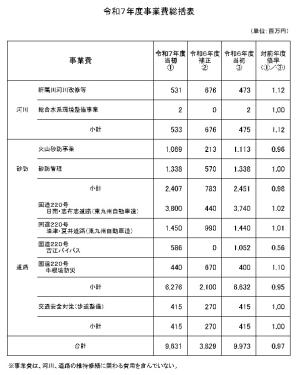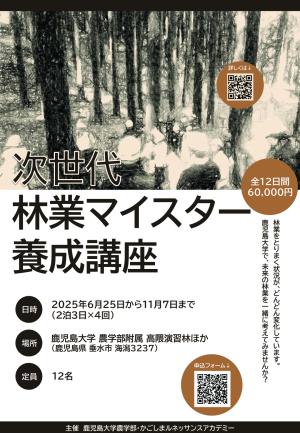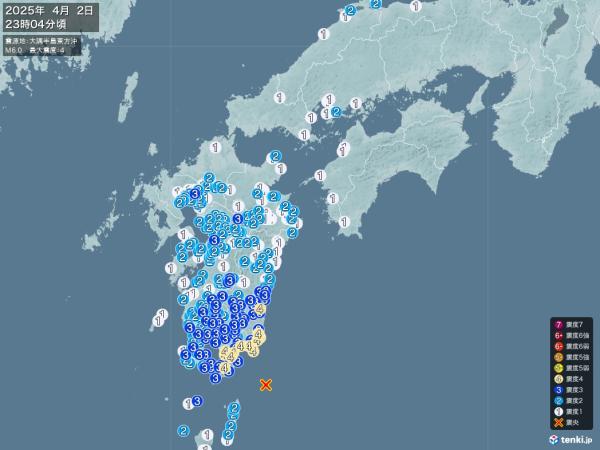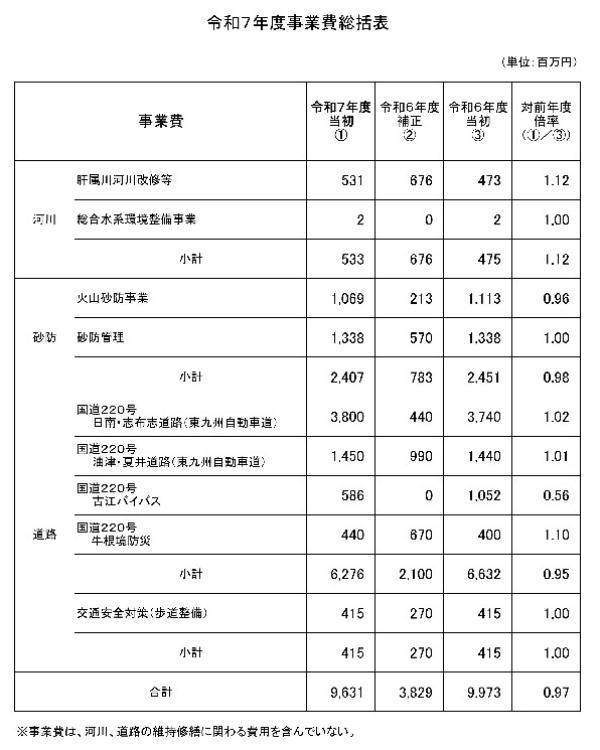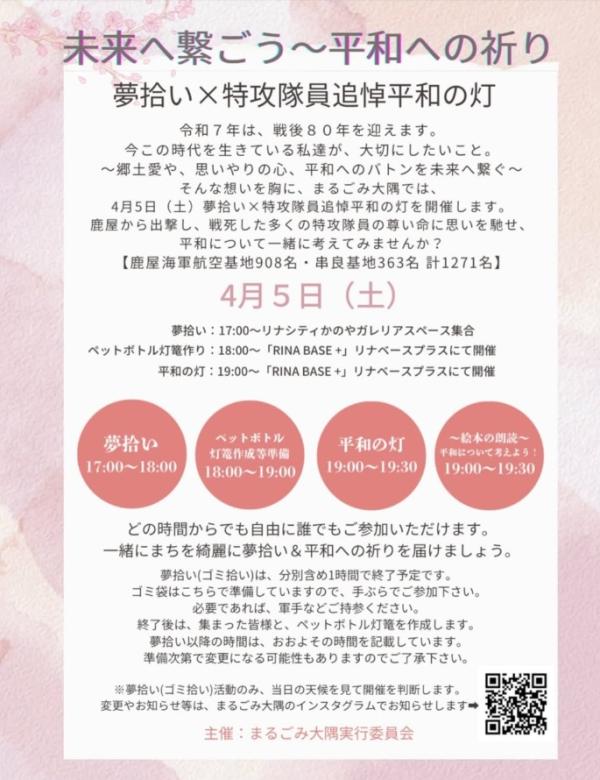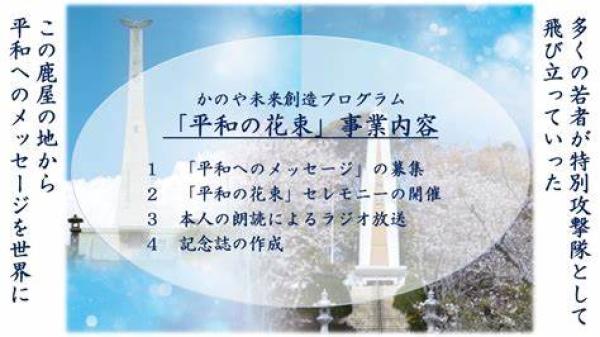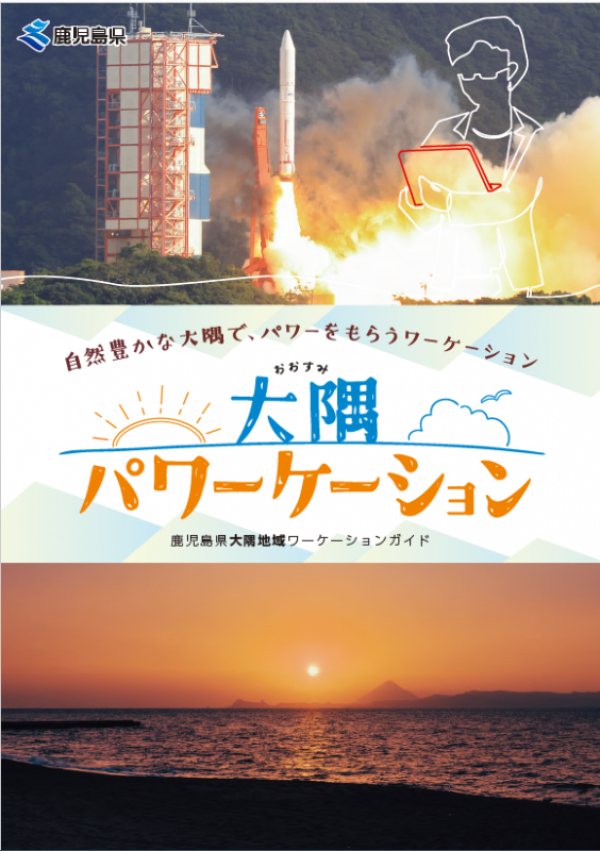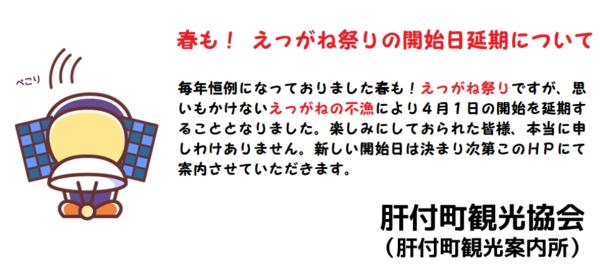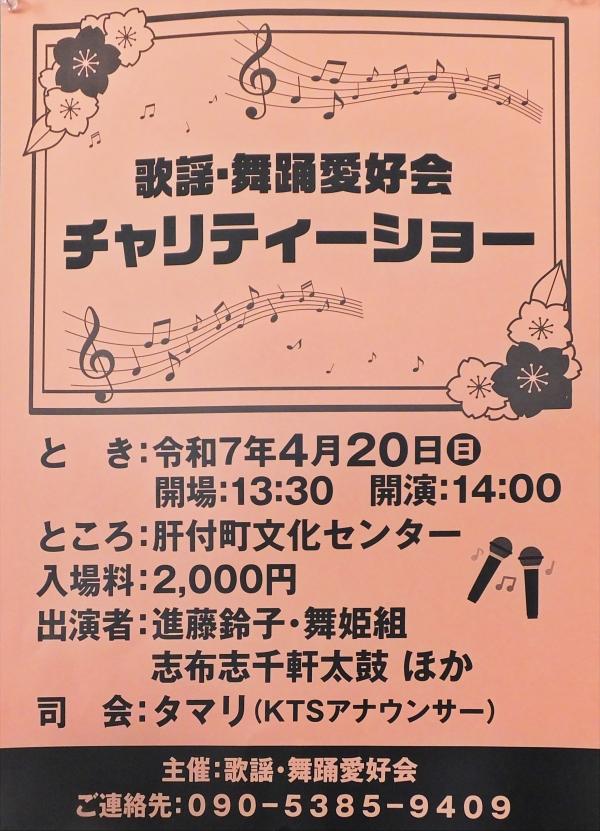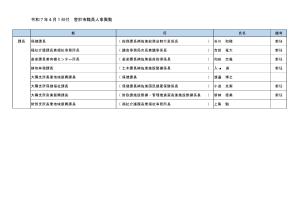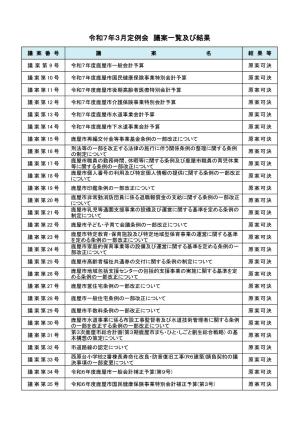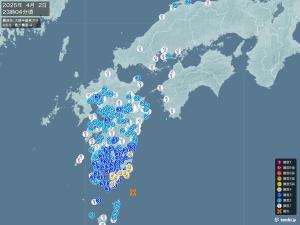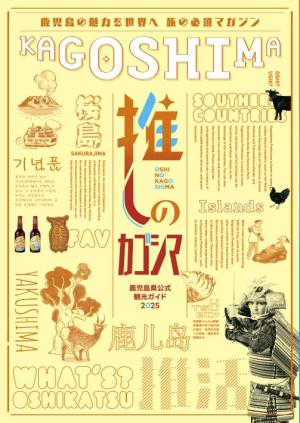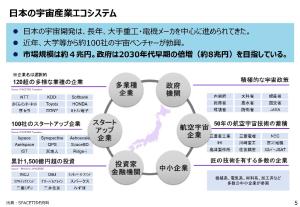《雑草 》
こどもは、自ら求め、自ら決め、自ら動き出す力を持ってる
不登校やひきこもりに対しては、平成19年前後、大隅倫理法人会で中村文昭さんを講師に呼んで聞いた内容、引きこもりやニートたちを北海道に集め、農業を通して自立することを学べるように展開する「耕せにっぽん!」という話。
ひきこもりやニートに対して実際活動し、彼らが農業すれば社会問題、『若年者就労問題』と『食糧自給率の低下問題』が一気に2つ解消する…ということに共鳴。

こちらだったらと、ひきこもり焼酎「親泣かせ!」を作ったりするのを手伝った。そのときはひきこもりが耕したというわけではなく、まずは形にということで何か糸口をつかんで…ということだったが、その後、何もできないでいた。
そして、DVや虐待のこどもに対しての現実を見て、相談もあって空いている部屋にしばらく泊めたことあったりで、20数年前ころからとても気になっていることでもあった。
そして一昨年だったか、自主映画「夢見る小学校」を観て、「じぶんのままでいいんだよ」という学校のスタイル。
文科省の学習指導要領が、2020年度から「探求学習」に大きく舵を切りました。
30年前から「探求学習」を実践している先進的な学校があります。
宿題がない、テストがない、先生がいない、「きのくに子どもの村学園」。キラキラした目で授業を受ける小・中学生の姿を見た事がありますか?
学校って、本当はこんなにわくわくする場所だったのです。「学校教育」の認識が180度変わる「衝撃の楽しい授業風景」。
学園の子どもたちが、「プロジェクト」とよばれる体験学習の授業を通じて、自分たちでプロジェクトを運営し自らの頭で考えていく姿…がそこにあった。
Educationには、教える(teaching)という要素無し
また、60年間成績通知表や時間割りがない「体験型総合学習」を続ける公立小学校の伊那小学校。通知表の学習評価を「選択性」にした松山市立余土小学校。校則、定期テストをやめた世田谷区立桜丘中学校などの例。
特に、きのくに子どもの村学園では、教えるというより、子どもたちが自ら学ぶというスタイル。それでもちゃんと文科省下での学校だ。
夢見る小学校上映会終了後は、子どもの村学園に子供を通わせ、学園にも関りある音楽教師、大友剛さんによるトークショーもあってとても興味深く聞いた。
その中でも、教育とは何ぞやということ、英語のEducationには、教える(teaching)という要素は入っていない。
引き出す、呼び起こす、人間の内面にあるものを呼び戻すことであり、まさに正反対の訳がしてある。
小学館の大辞典では、教育とは、ある人間を望ましい姿に変化させるために心身両面にわたって意図的、計画的に働きかけること…などと訳してある。
洗脳とは、特異な環境下で一貫した徹底的な教育を行い、従来持っていた思想信念などを洗い流して新しい思想、信念を植えるけること、程度の差、手法の巧拙はあれあらゆる教育が洗脳である…とも説明。
少し極端かな…とは思ったりもしたが、今の子どもたちが不登校になったり、ひきこもりになったりするのは、今の学校のスタイルに合わない子どもたちがいっぱい増えてきている…ということなのだろう。
学校は職場ではなく、こどもと教師の人生の邂逅の場
60年間通知表と時間割のない総合学習が続けられている伊那小学校の理念は、こどもは、自ら求め、自ら決め、自ら動き出す力を持っている。
校長は「学校は職場ではなく、こどもと教師の『人生の邂逅(かいこう・めぐりあうこと)の場』であってほしいと願っています」という。
松山市立余土小学校では、学校の体育館で「夢見る小学校」を上映しました。先生たちとも相談して宿題を大幅に減らしました。通知表の学習評価記載は、希望する保護者のご家庭には評価を記載しない、「通知表選択性」に変えました…という。
きのくに子どもの村学園を卒業した子どもたちは、中高生になると生徒会長や、大学でも答辞や送辞を読んだりし、就職は大企業が引っ張りだこ。自分たちで解決しようとし、リーダーシップをとれる人材だからだという。
こうした学校単位でのアクションに対して文科省では、どう考えているのだろうか…。
2020年度、子供の学びが進化します!新しい学習指導要領、スタート!と題して次のことをPRしている。
学校が変わる、それは足し算でなく、引き算
グローバル化や人工知能・AIなどの技術革新が急速に進み、予測困難なこれからの時代。子供たちには自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動し、よりよい社会や人生を切り拓いていく力が求められます。
学校での学びを通じ、子供たちがそのような「生きる力」を育むために、学習指導要領が約10年ぶりに改訂され、2020年度より小学校から順に実施されます。
小学校中学年から「外国語教育」を導入、小学校における「プログラミング教育」を必修化するなど社会の変化を見据えた新たな学びへと進化します。
しかし、何かしっくりこない。
誰一人取り残されない学びの保障を社会全体で実現を考えるときベースとなること、先の大友さんの話の中で、どうしたら子どもファーストで学校が変わるか、それは足し算でなく、引き算だという。(米永20241113)