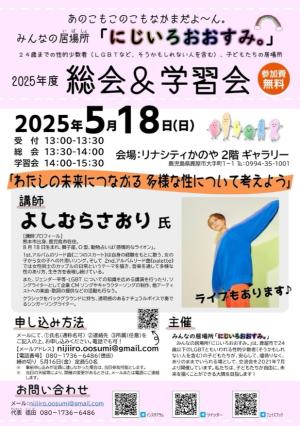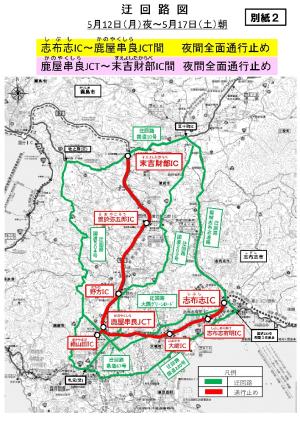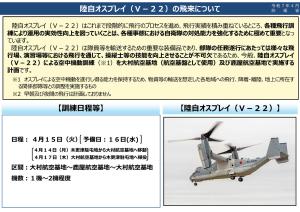《雑草 》
令和のおコメ騒動と保護主義、千載一遇のチャンスか
令和のおコメ騒動。
これまでの農業政策の歪みが露呈し、消費する側に大きな負担を掛けている。これに農水大臣の発言で、フラストレーションはたまっていく一方なのか。
いろいろな論評があり、減反政策強化と猛暑で、昨年夏から秋にかけての供給分が不足。
その後に消費される予定の米を先食いしてしまい、その結果で、今現在までの供給分まで加え、合わせて40万㌧が不足していたのに、それを農水省がコメ不足を認めたがらず、消費者にとっては理解しづらいことだが、備蓄米を放出しても米価を下げたくないという思惑が重なって、今現在があるという。

農水省は、備蓄米放出で、消費者に近い卸売業者や小売業者ではなく、放出に反対してきたJAに販売。
また、備蓄米が放出されされたものの、農水省は1年後に放出量と同量を買い戻すという条件を付けた。
米価上昇で今年生産者が生産を増やしても、それを上回る量を市場から回収すれば、その時点で米価はまた上昇する。
慌てて先週、備蓄米の買戻し期限を、1年後から原則5年以内に延長することに決めたというが、それでも米価は下がる気配はない。
食に対する様々な疑問を持つ中で、いろんな情報が入り昨年、鹿児島大学構内で行われた東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘氏の講演を聴きに行った。
食料・農業問題の本質と裏側を、様々な事例を挙げて指摘。
種子法廃止や種苗法改正についても、なぜこうした農家を潰すようなことをするのだろうという思いで、講演を聴いた。
農業政策を根本から構造的に考え直すとき
農家の後継者不足も耕作放棄地の拡大も、農家や消費者側に向いていない農業政策では、半ば当たり前の結果では…とも感じながら、何か割り切れない気持ちで帰途についた。
特に大隅半島は、高隈山系、国見や稲尾山系があり、中山間地域が多い中、この地域でも大規模農業やスマート農業推進という掛け声の大きさにも、何か腑に落ちないものがあった。
そして今回の令和のおコメ騒動。
これは日本の主食であるお米に関しての大きな転換点になるであろう一方で、単に米一つだけのことでなく、農政の構造的な問題を考える大きなチャンスでもあるのだろう。
日本の食の自給率の異常な低さも含めて。
歪んで行き過ぎたグローバル経済を立て直す?
そして、今のトランプ関税。
保護主義を推し進め、今の歪んで行き過ぎたグローバル経済を立て直すという。
今ある日本の農業政策を考えてみると、戦後の食糧難政策として、米国からの脱脂粉乳や小麦などが持ち込まれた。
その後も、自由貿易という名のもとでの工業化された米国の農産物が、日本の農業の根本を変えたとも言えるのではないか。
そして今度は逆に、自由貿易から保護貿易という。
日本では今回のおコメ騒動で、米だけでなく今の農業政策をも大きく転換していく大きなチャンスということに加え、米国が大きな方向転換をしているこのタイミングこそが、内からと外からのまさに千載一遇の機会とも言えるのでは…と思ったりもする。
国会中継を聞いていても、そうした論争にはなってないようだが…。
特に主食であるコメを通して、後継者不足や耕作放棄地対策を改めて考えてみる、というより、国民にとって安心できる主食とは何かを、これまでとは違った新たな視点で、国も地方も消費者としての国民もともに考えていく。
単なる令和のおコメ騒動で済ますのでなく…。
海外でもインバウンド客でもおにぎり人気で、お米の需要が高まっていると聞くし、小麦パンだけでなく米粉パンも人気、日本の白米はとても美味しいが、よりヘルシーに玄米として食べることも含め、もっとできることがあるような気がする。
後継者不足や耕作放棄地解消、消費者のためにも
日本の米の自給率は100%だというが、全体では38%。
内外の環境を見て構造的に日本の農業を変えるビッグチャンスなのだろうが、小手先の対策や、大臣の発言等を耳にして撤回はされたものの、とてももどかしい思いだ。
国の動きもだが、今、田植え時期で、この地域でも一面に広がる水田の中を車で走らせたりするが、田舎に行けば行くほど自分の食べる米は、自分たちで作り、おすそ分けしたり、近所で分けてもらったりしているようだ。
食の供給基地もだけど、米だけでなく野菜も、昔八百屋があったようなスタイルには戻せないのかもしれないが、それぞれの生活圏の中で、地元のスーパーや直売所、道の駅があったり、自分たちの食べる野菜は身近に買い求めるスタイルを、その地域の中で作り上げていくと、また農のかたちも少しは変わってくるのではないかとも考えたりする。
それが構造的な変化に直で繋がるわけではないのだろうが、消費者の意識も変わるだろうし、食そのもの、フードマイルなど経済の循環も含め地域が豊かになるのでは。
地方から変わっていく…変えていく、今の国政、与野党の攻防もを見ていて、地道にそう思う。
後継者不足や耕作放棄地解消、そして私たち消費者のためにも…。(米永20250520)
















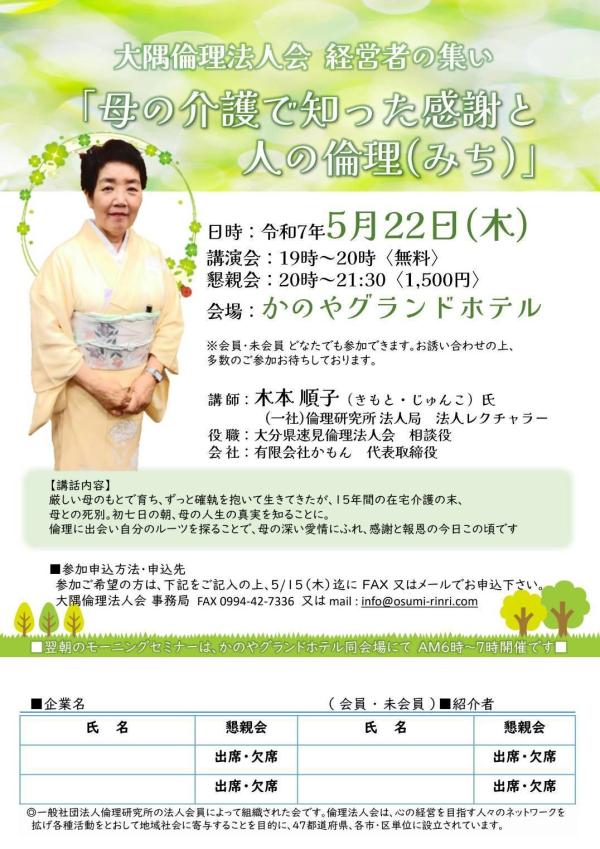
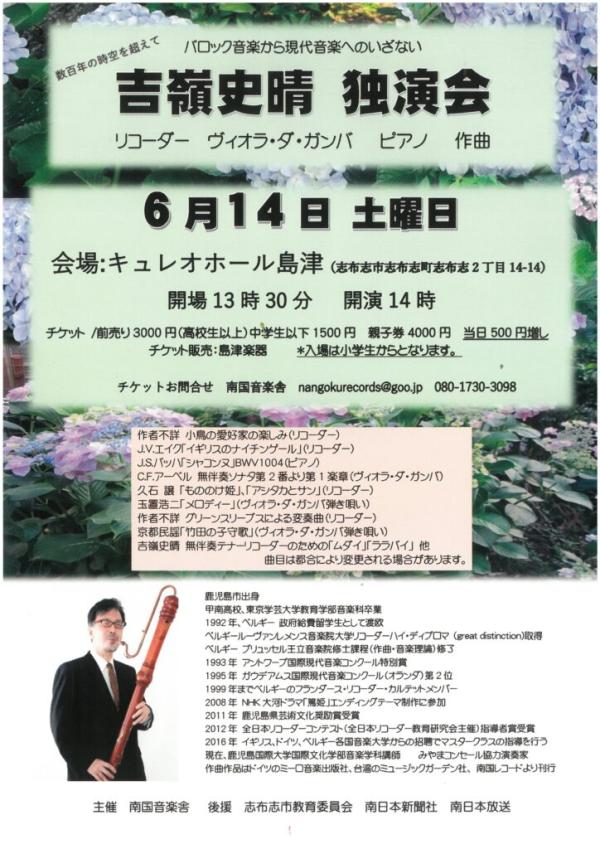


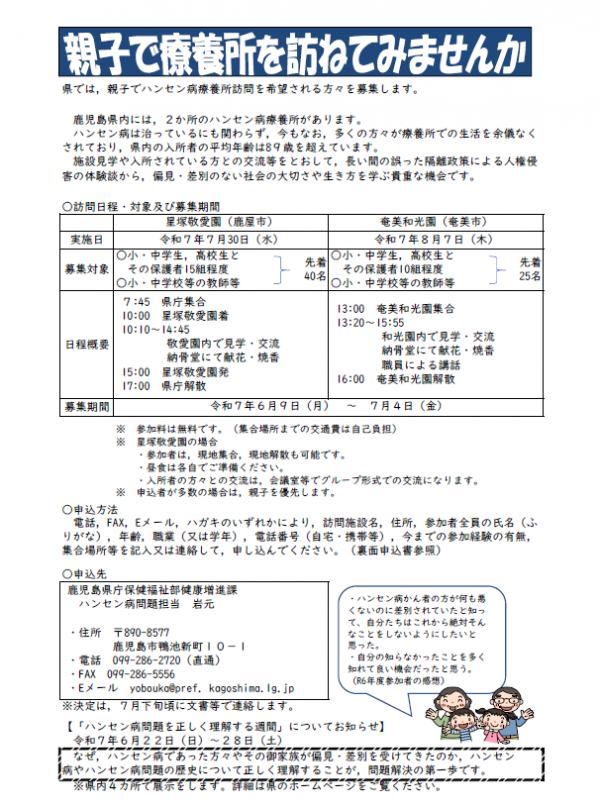







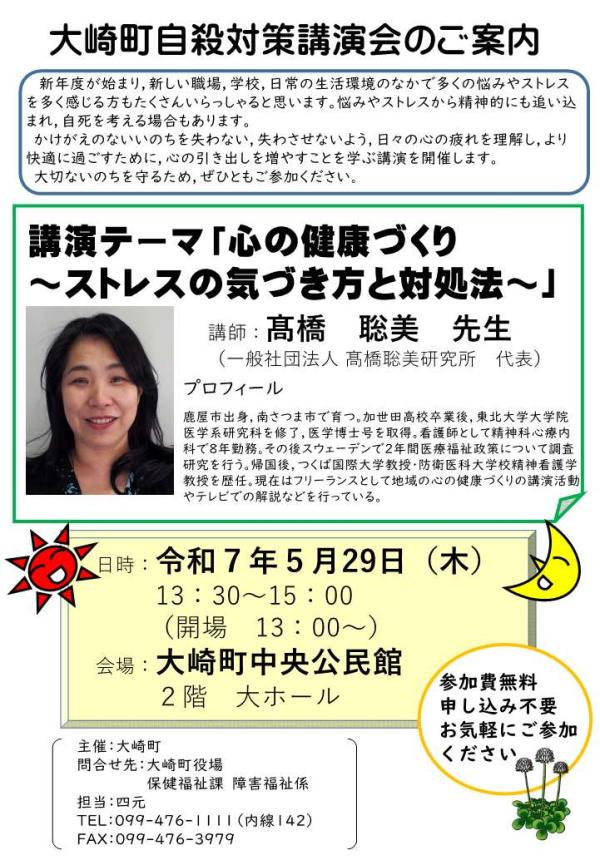






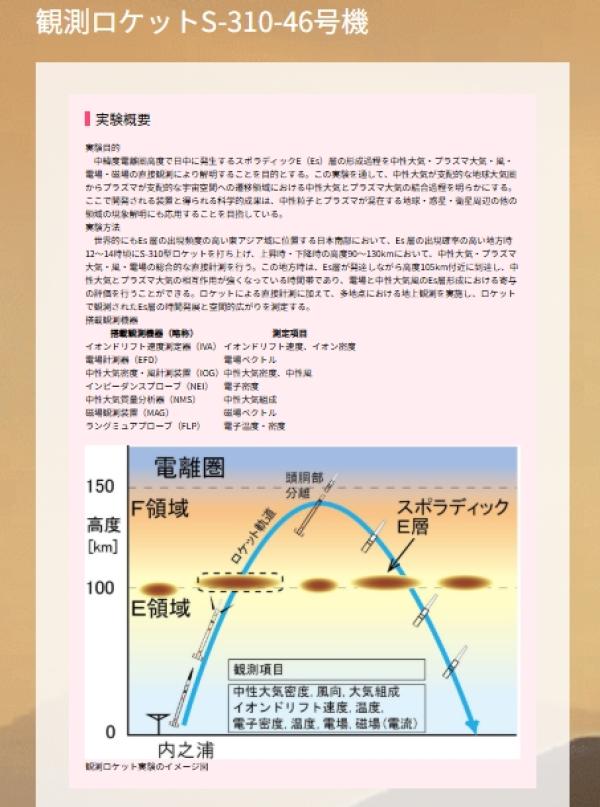



.jpg)