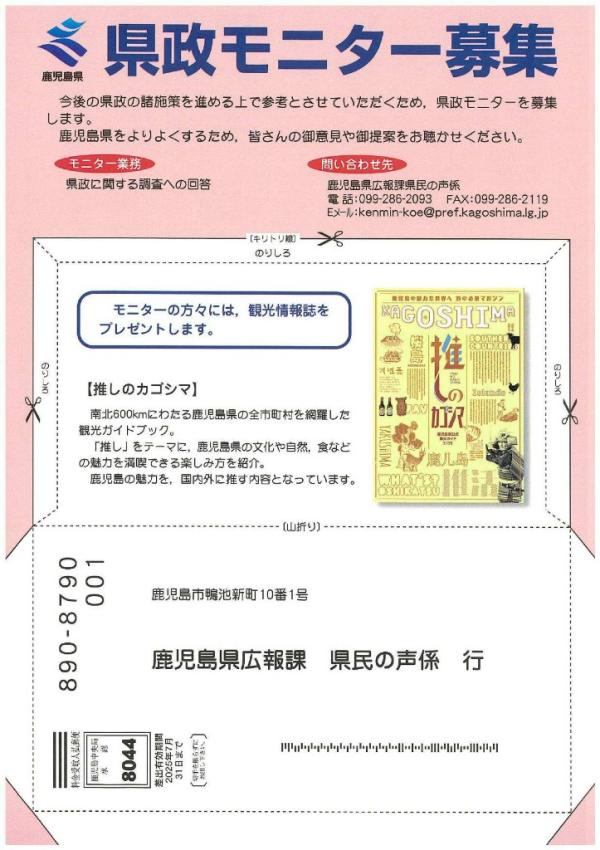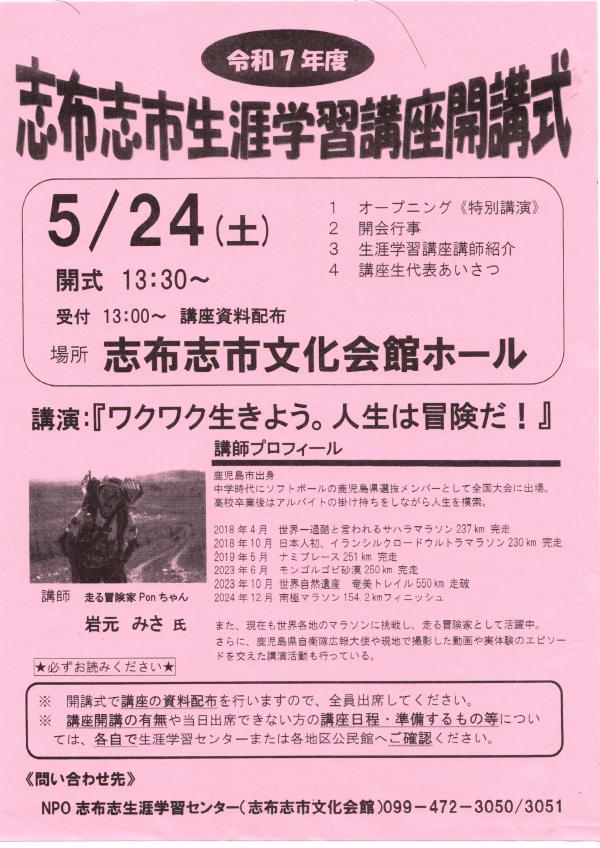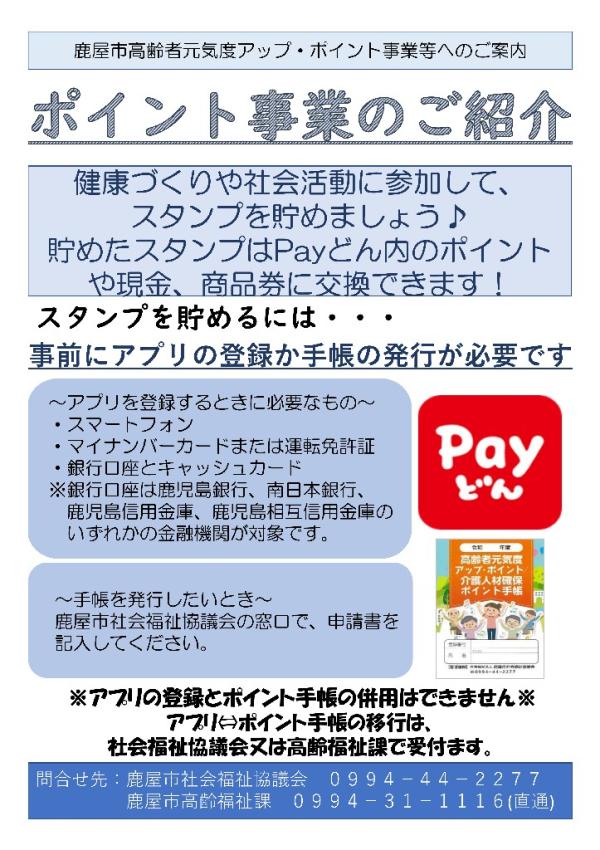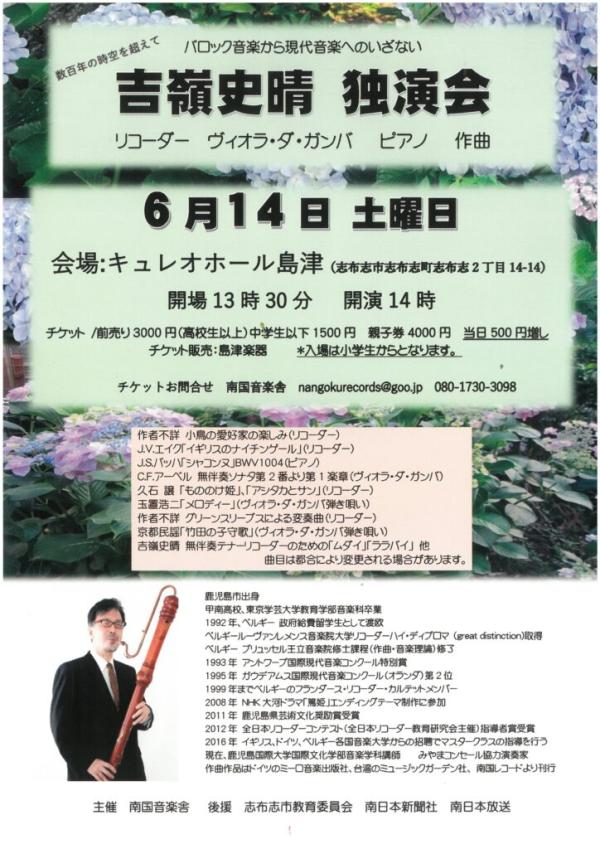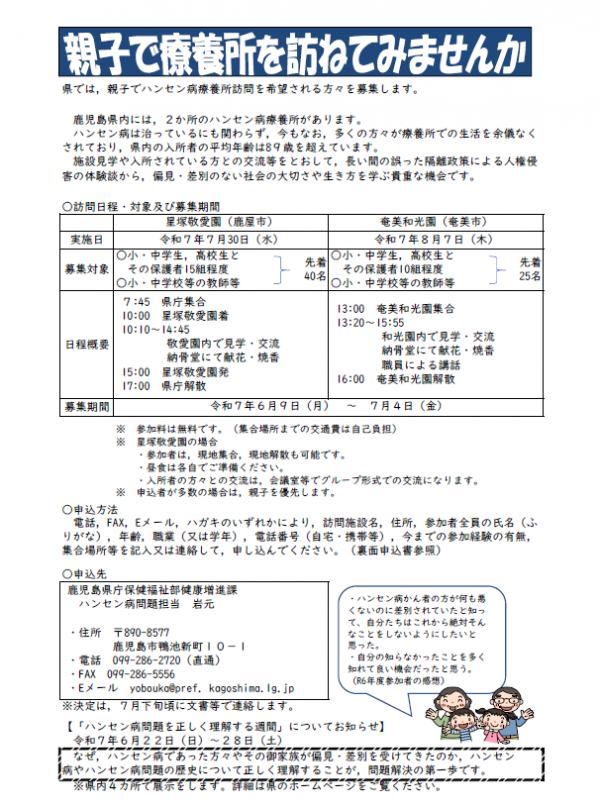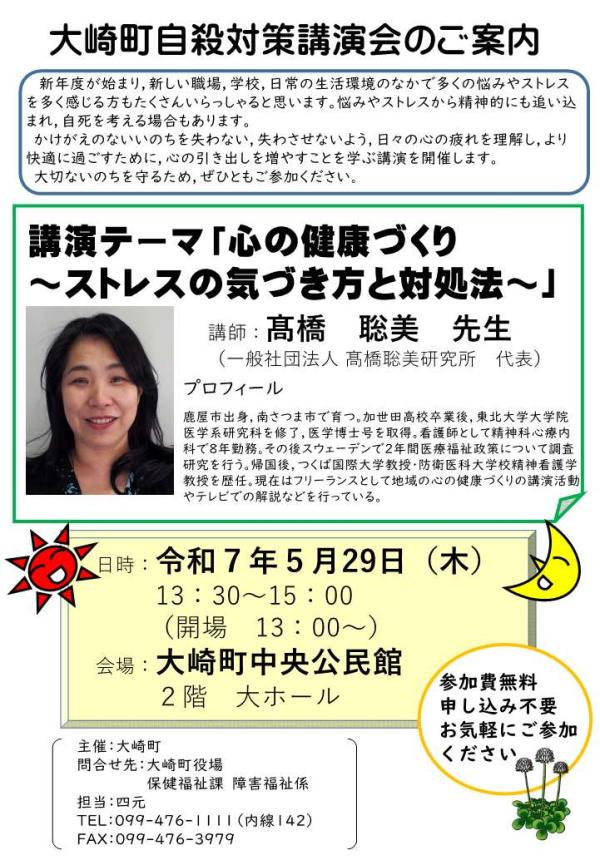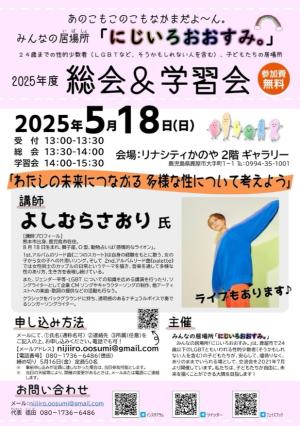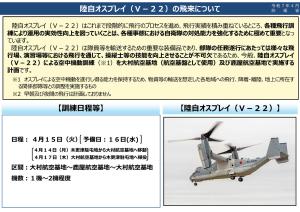《行政 》
南海トラフ地震で自治体の備えや弱者配慮は 県民防災講演
令和7年度県民防災講演会が、令和7年5月17日、コミュニティセンター志布志市文化会館で開催され、南海トラフ地震に関連する情報などについて学んだ。
県では,鹿児島地方気象台と鹿児島大学地域防災教育研究センターとの共催により,南海トラフ地震に関する知識と理解を深め,防災意識の高揚を図るため次の内容で開催。

▽南海トラフ地震に関連する情報~南海トラフ臨時情報と取るべき防災対応~
鹿児島地方気象台地震津波火山防災情報調整官安藤忍氏
▽自治体における大規模地震災害への備え~自治体としての備えと対応~
志布志市水道課課長(前危機管理監)萩原政彦氏
▽誰もが安心できる環境をめざして~災害時要配慮者の視点から考える~
鹿児島大学医学部保健学科(兼地域防災教育研究センター)助教日隈利香氏

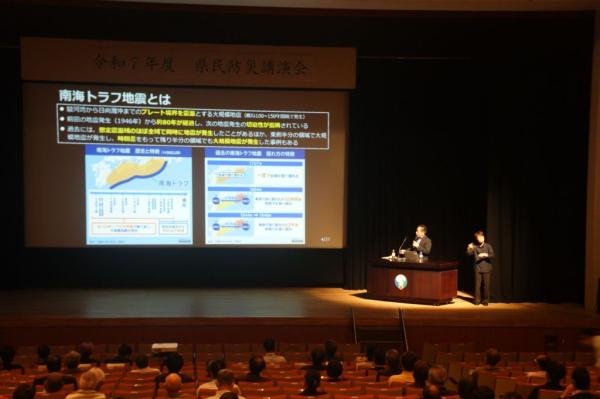
安藤氏は、南海トラフ地震について、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として概ね100~150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震。
前回1946年から約80年が経過し、次の発声の切迫性が指摘されている。
静岡から宮崎にかけて一部では震度7となる可能性があり、関東から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波の襲来が想定されている…として、そのモーメントマグニチュード、規模、津波の高さや速さ、増幅の仕方などを説明。
突発的に発生、地震は一度では終わらない…とする地震への備えを日ごろから実施すべき。
令和6年8月8日に発表された南海トラフ臨時情報(巨大地震注意)では、政府や⾃治体などからの呼びかけ等に応じた防災対応を。
その想定震源域の住民には1週間を基本として備えの再確認をした上で、通常の生活を続けること。
30年内に80%という発生確立とされており、いつ発生するかわからない。
日ごろからの地震の備え、緊急地震速報が発表されたら…などの説明があった。


萩原氏は、自治体としての地震への備えと対応として、令和6年8月8日の日向灘地震発生時における志布志市の対応について、新型コロナウイルス感染症蔓延防止からの防災対策、その意識を高めることの難しさがあること。
どこに避難すればいいか、その経路など、余地の困難な地震、津波からの減災対策は、平時からの自助、共助を高めて…など説明し、令和4年度の県総合防災訓練の様子や、出前講座、高齢者サロンでの防災講演の実施。
避難所開設や運営、避難の呼びかけについて令和6年8月で実際行った例を挙げ、地震や水害に備えた助成事業のことについても説明した。

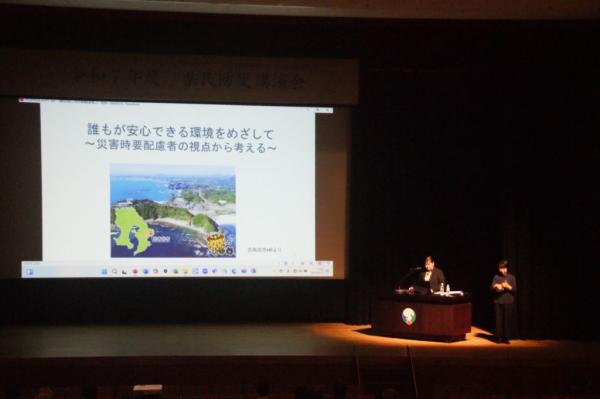
日隈氏は、世界の0.2%の国土で、災害の20%が日本で派生している災害大国ニッポンの過去の地震被害。
能登半島地震でのニュースの在り方、社会的弱者の情報のこと。1年経ってもなかなか復興が進まない現実。
ビニールハウスやビニールテント内で生活する住民など見て、実際、フェリーと車を使って現地に出向いて現地調査、輪島から羽咋郡、七尾市などでの社会的弱者や職員、市民などの話を聞いた経験を話した。
そうした体験をもとに、志布志市で発生した場合はどうなのか。
被害を減らすには何が必要なのか、能登半島地震を元に南海トラフ地震を考え、高齢者のケースなど具体的な事例検討について説明を行った。